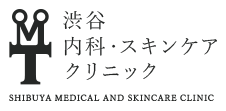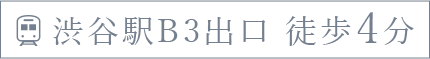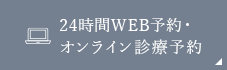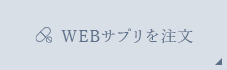貧血とは
 貧血とは、血液中の赤血球数が少ない状態を指します。血液は全身に酸素や栄養を運搬する役割がありますが、特に酸素は、赤血球に含まれるヘモグロビンという物質と結合することで運ばれます。従って、ヘモグロビン量が低下すると身体に十分な酸素を送り届けることができなくなり、様々な症状が現れるようになります。
貧血とは、血液中の赤血球数が少ない状態を指します。血液は全身に酸素や栄養を運搬する役割がありますが、特に酸素は、赤血球に含まれるヘモグロビンという物質と結合することで運ばれます。従って、ヘモグロビン量が低下すると身体に十分な酸素を送り届けることができなくなり、様々な症状が現れるようになります。
貧血を引き起こす原因には様々なパターンがありますが、中には命の危険を伴う重篤な疾患が関与しているケースもあるため、気になる症状が続いている場合には自己判断で放置せずにできるだけ早く当院までご相談ください。
人によって貧血の目安は違う?
以下は、正常な状態の血中ヘモグロビン量の目安となります。
| 成人男性の場合 | 13~14g/dL未満 |
|---|---|
| 成人女性の場合 | 12g/dL未満 |
| 80歳以上の場合 | 11g/dL未満 |
| 妊娠中の場合 | 10.5~11g/dL未満 |
貧血の症状
貧血の主な症状は、めまいや立ちくらみ、動悸、息切れ、全身倦怠感、疲労感、耳鳴り、味覚異常、蒼白、口内炎、口角炎などが挙げられます。
貧血セルフチェック
まぶたの裏側の皮膚の色を確認する方法があります。
通常であればまぶたの裏側の皮膚は赤く充血した色をしていますが、貧血状態になると蒼白に変化します。
貧血の原因について
以下は、貧血を引き起こす主な原因となります。
- ヘモグロビンを構成している鉄分が不足している
- タンパク質などが不足して赤血球やヘモグロビンの生成量が低下している
- 身体のどこかが出血を起こして赤血球が減少している
- 身体のどこかが炎症を起こして赤血球が消費されている
- 何らかの異常によって赤血球やヘモグロビンが破壊されている
- 赤血球の元となる幹細胞が異常を起こしている
- 巨赤芽球性貧血・悪性貧血などによってビタミンB12や葉酸が不足している
- 感染症に罹患している
- 溶血性貧血や肝硬変などに罹患している
- 再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・赤芽球癆・腎性貧血などの疾患によって血液の生成量が低下している
- がんや関節リウマチなどによって自己免疫を起こしている
など
貧血の種類
貧血は、原因に応じていくつかの種類に分類されます。主な分類は以下となります。
鉄欠乏性貧血
血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンは、呼吸によって取り入れた酸素を身体全体に運搬する役割を担っています。従って、偏った食事習慣や出血などによってヘモグロビンの主成分である鉄分が不足すると、ヘモグロビンが十分に生成できなくなって貧血を引き起こします。
再生不良性貧血
再生不良性貧血とは、血液中の赤血球や白血球、血小板のもととなる骨髄の血幹細胞が減少することで血液のあらゆる成分が不足し、慢性的な貧血を引き起こす病気です。
二次性貧血(続発性貧血)
二次性貧血(続発性貧血)とは、他の原因疾患によって二次的に引き起こされる貧血のことを言います。貧血を引き起こす主な原因疾患としては、細菌・ウイルスによる感染症や膠原病、関節リウマチ、長期間の炎症による赤血球の減少、肝臓・腎臓機能の低下、糖尿病性腎症、慢性腎臓病(CKD)、胃がん、大腸がん、甲状腺の機能障害などが挙げられます。
悪性貧血
悪性貧血とは、赤血球の生成に必要なビタミンB12や葉酸が減少することで赤血球の量が減少し、その結果引き起こされる貧血です。主な原因は、過度な飲酒による葉酸不足や胃の手術などによって胃酸の分泌量が減少することでビタミンB12の吸収率が低下することなどが挙げられます。
貧血の原因は
腎臓が原因かもしれません
血液中の赤血球は、腎臓から分泌されるエリスロポエチンというホルモンによって生成が促進されます。そのため、何らかの原因によって腎臓機能が低下すると、エリスロポエチンの分泌量が低下して赤血球の生成量が減少し、貧血を引き起こします。このように、腎臓の異常が原因で引き起こされる貧血を腎性貧血と言います。
腎性貧血の症状
 腎性貧血の主な症状は、めまいや立ちくらみ、全身倦怠感、疲労感などが挙げられます。しかし、一般的に腎臓の機能障害は緩やかに進行するためにこれらの症状も少しずつ出現し、身体が変化に順応してしまうことで本人も異常に気付かないケースが多く見られます。腎不全は本人も気付かないうちに病状が進行していることがあるため、定期検診等で常に血液の状態を確認しておくことが大切です。
腎性貧血の主な症状は、めまいや立ちくらみ、全身倦怠感、疲労感などが挙げられます。しかし、一般的に腎臓の機能障害は緩やかに進行するためにこれらの症状も少しずつ出現し、身体が変化に順応してしまうことで本人も異常に気付かないケースが多く見られます。腎不全は本人も気付かないうちに病状が進行していることがあるため、定期検診等で常に血液の状態を確認しておくことが大切です。
貧血やそれに伴う症状が長期間継続している場合には、自己判断で放置せずに速やかに医療機関を受診して適切な検査や治療を受けるようにしましょう。
腎性貧血の治療
 腎性貧血の治療では、エリスロポエチン製剤の注射や赤血球造血刺激因子製剤(ESA)の内服、鉄剤の内服などが適用されます。
腎性貧血の治療では、エリスロポエチン製剤の注射や赤血球造血刺激因子製剤(ESA)の内服、鉄剤の内服などが適用されます。
腎性貧血の治療目標
慢性腎臓病(CKD)による腎性貧血の治療の際には、ガイドラインに則ってヘモグロビンの値を11g/dL~13g/dLの範囲に改善することが目標となります。この範囲を超えた場合には、減薬や休薬によってエリスロポエチン製剤や赤血球造血刺激因子製剤(ESA)の量を抑えて調整します。ただし、血管や心臓の病気の治療を並行して行っている場合には、ヘモグロビンの値が12g/dLを超えた時点で減薬や休薬を検討することもあります。