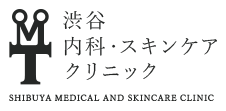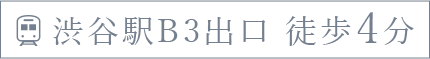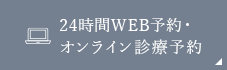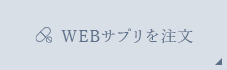生活習慣病と診断されたら
当院まで
 生活習慣病とは、食生活の乱れ、運動不足、睡眠不足、タバコ、飲酒、ストレス等の生活習慣によって発症・進行する慢性疾患の総称を言います。 当院は地域のかかりつけ医として、生活習慣病の予防や早期発見のため定期検診をおすすめしています。
生活習慣病とは、食生活の乱れ、運動不足、睡眠不足、タバコ、飲酒、ストレス等の生活習慣によって発症・進行する慢性疾患の総称を言います。 当院は地域のかかりつけ医として、生活習慣病の予防や早期発見のため定期検診をおすすめしています。
まずは診察の上、血液や尿検査による病状の把握をし、一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせて生活習慣に関する相談やアドバイスを親身に行います。
また必要に応じてお薬の処方など適切な治療や管理も行います。大切なご家族やご友人のためにも生来健康でいるために、症状がなくてもお気軽にご相談ください。
生活習慣病内科 診療実績
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2023年 | 658件 |
| 2024年 | 1742件 |
代表的な生活習慣病
生活習慣病について
 代表的な生活習慣病には、「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症(高脂血状態)」「高尿酸血症(痛風)」が挙げられますが、そのほか、冠動脈障害を含む「心疾患」、脳梗塞や脳出血などの「脳血管障害」、「肝疾患」「腎疾患」「膵臓疾患」も生活習慣病に含まれます。他には、睡眠中の無呼吸によって血管に負担がかかり様々な重大疾患の元となる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」なども生活習慣病に分類されています。
代表的な生活習慣病には、「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症(高脂血状態)」「高尿酸血症(痛風)」が挙げられますが、そのほか、冠動脈障害を含む「心疾患」、脳梗塞や脳出血などの「脳血管障害」、「肝疾患」「腎疾患」「膵臓疾患」も生活習慣病に含まれます。他には、睡眠中の無呼吸によって血管に負担がかかり様々な重大疾患の元となる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」なども生活習慣病に分類されています。
がん
がんは口腔、食道、肺、胃、大腸、子宮や卵巣、前立腺などの内性器、皮膚、骨など身体のどの部分にがんができるかによって、痛み、全身倦怠感、不正出血など、症状は様々です。
その発症のメカニズムは少しずつ解明されてきてはいるものの、未だ不明な部分も多い状態です。
ただし、一部のがんは生活習慣の偏りによって発症しやすくなったり、進行しやすくなったりすることが分かっており、生活習慣病として考えられるようになりました。
心疾患
先天的な心臓の構造的な異常などを除く心臓病の多くは、心臓へ向かう冠動脈などが動脈硬化を起こすことが原因とされ、心臓への血流が滞り、心筋への酸素や栄養が不足することで生じます。
いったん冠動脈障害が起こると、胸痛、動悸・息切れ、全身疲労感、めまい、不整脈などの症状を起こし、放置すると生命に関わる事態となります。 冠動脈障害や心筋の障害が起こる原因の多くは、高脂血症、高血圧、過度の飲酒、喫煙習慣といった生活習慣が関わっており、生活習慣病に分類されています。
脳血管疾患
脳の血管に何らかの障害が起こる脳血管疾患には、脳梗塞、脳出血などが挙げられます。主に、動脈硬化による血管の損傷や血流が滞ることで生じます。
偏った食生活、飲酒や喫煙習慣、生活の乱れ、ストレスなどが原因となることが多く生活習慣病とされています。脳のどの部分に障害が起こるかによって症状は異なりますが、激しい頭痛、ろれつが回らない、言葉が出てこない、意識レベルが低下する、左右どちらかの半身麻痺などが主な症状です。
肝疾患
肝臓は大きな臓器で細胞数も多く、肝炎、脂肪肝、肝硬変など、肝臓に障害が起きても自覚症状がないまま進行する特徴があります。
進行すると、腹部膨満感、疲れやすさ、食欲の低下などの他、重篤化してくると便や尿の色の変化、黄疸といった症状も現れます。
肝疾患は高脂質状態や高血糖、高血圧症などの生活習慣病、過剰な飲酒や喫煙といった生活習慣の偏りによって発病しやすくなるため注意が必要です。
腎疾患
腎臓の病気はなかなか自覚症状が現れにくく、沈黙の臓器と呼ばれることもあるほどです。
腎臓には尿を作るために多くの細い血管が集まっており、それが障害されることによっておこる糖尿病腎症は特に生活習慣に関わる腎疾患の代表的なものです。
その他の要因として、高血圧、高脂血状態などの他、過度の飲酒や肥満、ストレスなどの心因的な要素なども腎疾患のリスクを高めるため注意が必要です。病態が進行すると、頻尿や乏尿・無尿、血尿など尿の変化や水分調節の不良による浮腫、倦怠感、食欲の低下といった全身症状が現れることもあります。
膵疾患
膵臓は消化に必要な膵液を分泌し、血中の糖質のコントロールに必要なインスリンというホルモンを分泌する役割を果たしています。
膵炎(慢性・急性)、膵臓がんなどに代表される膵疾患は、脂質に偏った食事、運動不足といった生活習慣、それによる肥満、過度な飲酒や喫煙習慣、ストレスや過労などで発症する可能性が高くなることが知られています。
膵疾患になると、みぞおちの激しい痛み、食欲不振、吐き気や嘔吐、便通異常といった消化器症状、血糖値のコントロール不良などの症状が現れます。
下記に心当たりのある方は
早めの受診をおすすめします
- 検診で血糖値・血圧・尿酸値・中性脂肪が高いと指摘されたことがある
- 家族や親戚に糖尿病の人がいる
- 40歳以上である
- 20歳の時と体型が変わった
- 最近体重が増加した
- タバコを吸う
- 飲酒の機会が多い
- 睡眠時間や休養が少ない
- ストレスが多い
- 夜10時以降に飲食をすることが多い
- 食べるのが早い
- 食べ過ぎている
- 炭水化物が好き
- 野菜や果物を摂る習慣がない
- 外食やレトルト食品が多い
- 濃い味付けや炒め物、脂っぽい食事が多い
- ほぼ毎日間食する
- 体を動かす習慣がない
- 移動手段に車をよく使う
など
生活習慣病を放っておくと
 現在日本人の死因の上位を占めるがんや心筋梗塞、脳卒中は生活習慣病です。また心筋梗塞や脳卒中の要因となる糖尿病、高血圧症、脂質異常症をはじめとする生活習慣病は多くの場合、自覚症状がなく進行していきます。
現在日本人の死因の上位を占めるがんや心筋梗塞、脳卒中は生活習慣病です。また心筋梗塞や脳卒中の要因となる糖尿病、高血圧症、脂質異常症をはじめとする生活習慣病は多くの場合、自覚症状がなく進行していきます。
放っておくと重篤な合併症や後遺症を引き起こし、半身麻痺や認知症、透析などによる健康寿命※の低下や最悪の場合突然死に至ることもあります。また、免疫機能が低下するため、様々な病気にかかりやすく、細菌・ウイルスによる感染リスクも高まります。
※健康寿命とは『寝たきりや介護などを必要とせず、健康で日常生活を支障なく送ることができる期間』のことを言います。
診察の流れ
1診察
 問診表をもとに医師が診察します。
問診表をもとに医師が診察します。
2検査
必要に応じて検査(採血・尿検査・エコー検査など)をおこないます。ごくありふれた症状から貧血、糖尿病、内分泌疾患、膠原病などの慢性疾患が見つかることがしばしばあります。
疑う所見がある場合には、評価と診断を適切におこなうため、一般の検査項目のほかに多数の項目が必要となります。ご不安な点がございましたら医師に直接ご相談ください。
3検査結果
当日中に検査結果がわかるものに関しては、医師から結果説明をいたします。
検査項目によっては数日かかるため、後日再来院していただく場合がございます。
4診断・治療
診察と検査結果から適切な診断と治療について説明いたします。必要に応じてお薬を処方します。より専門性の高い検査や治療が必要となった場合には各専門の医療機関にご紹介いたします。