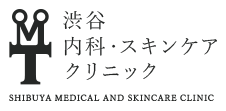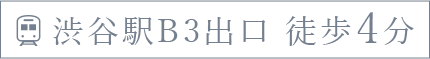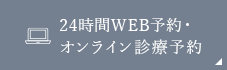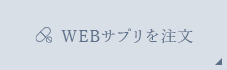糖尿病とは
 糖尿病は、血中の糖をコントロールするインスリンという物質が産生できない、または正常に働いていない状態です。血中の糖が高い高血糖状態が続くと、尿中に糖が排出され尿糖が陽性になります。
糖尿病は、血中の糖をコントロールするインスリンという物質が産生できない、または正常に働いていない状態です。血中の糖が高い高血糖状態が続くと、尿中に糖が排出され尿糖が陽性になります。
糖尿病になると、血中のブドウ糖濃度の上昇により血液がドロドロ状態になることで、血管に大きな負担がかかります。これは中枢を担う大きな血管から体の末端の毛細血管まで全身の血管で合併症が起こります。中でも糖尿病の三大合併症と呼ばれる、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性網膜症」「糖尿病性神経障害」は、腎臓の糸球体、眼の網膜内、手足の末梢の血管の障害で起こるものです。こうした三大合併症では、最悪の場合、人工透析、失明、手足の切断といった状態に陥ることもあります。一方、糖尿病による大動脈の障害では、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害や心筋梗塞などの、突然死や重篤な後遺症を残す恐れがある危険な合併症が知られています。こうした合併症を引き起こさないためには、糖尿病と診断されたら、速やかに血糖値をコントロールすることが大切です。
糖尿病と認知症
 糖尿病と認知症に関しては、これまで多くの研究が行われてきています。特に九州大学が福岡県糟屋郡久山町で継続的に行っている研究では、糖尿病の罹患者はそれ以外の方と比較して認知症になる可能性が1.7倍も高いという結果も報告されています。これは認知症全体の数値で、アルツハイマー型の認知症はこれまでの認識と異なり、糖尿病の罹患者の方が2倍も発症の可能性が高いという結果も報告されています。これは、糖尿病によって脳への血流が低下することで、アルツハイマー型認知症に特有の脳内物質であるアミロイドβたんぱくが蓄積しやすくなってしまうことから認知症のリスクが高まるのではないかと考えられている事象です。
糖尿病と認知症に関しては、これまで多くの研究が行われてきています。特に九州大学が福岡県糟屋郡久山町で継続的に行っている研究では、糖尿病の罹患者はそれ以外の方と比較して認知症になる可能性が1.7倍も高いという結果も報告されています。これは認知症全体の数値で、アルツハイマー型の認知症はこれまでの認識と異なり、糖尿病の罹患者の方が2倍も発症の可能性が高いという結果も報告されています。これは、糖尿病によって脳への血流が低下することで、アルツハイマー型認知症に特有の脳内物質であるアミロイドβたんぱくが蓄積しやすくなってしまうことから認知症のリスクが高まるのではないかと考えられている事象です。
他にも、HbA1cと計算能力の実験では、HbA1cの値が標準値より高くなることで、明らかな計算能力の低下が見られることも報告されています。
糖尿病のリスク・合併症について
狭心症・心筋梗塞
 糖尿病の進行によって、心臓に向かう冠動脈に動脈硬化が起こると、心臓への血流が悪くなるだけではなく、動脈が詰まった部分にできた血栓の塊が何らかのきっかけで剥離し血管で運ばれて重要な部分に詰まってしまうことで、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患の原因となります。狭心症はまだ心臓を構成する心筋にまでダメージが至っていない状況で、胸痛、動悸・息切れ等を主な症状としていますが、心筋梗塞は心筋自体に障害がおこってしまった状況で、正常な日常生活を送ることができなくなるばかりではなく、突然死のリスクも高くなってしまいます。
糖尿病の進行によって、心臓に向かう冠動脈に動脈硬化が起こると、心臓への血流が悪くなるだけではなく、動脈が詰まった部分にできた血栓の塊が何らかのきっかけで剥離し血管で運ばれて重要な部分に詰まってしまうことで、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患の原因となります。狭心症はまだ心臓を構成する心筋にまでダメージが至っていない状況で、胸痛、動悸・息切れ等を主な症状としていますが、心筋梗塞は心筋自体に障害がおこってしまった状況で、正常な日常生活を送ることができなくなるばかりではなく、突然死のリスクも高くなってしまいます。
近年心筋梗塞の治療はカテーテル治療などで画期的に進歩しましたが、それでも1度障害されてしまった心筋は元に戻ることがありません。こうした事態を起こさないよう、しっかりと糖尿病をコントロールしておくことが大切です。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)
糖尿病によって脳へと出入りする血管に動脈硬化が起こると、脳の血流が損なわれて、正常に脳が働くことができなくなります。これは心筋梗塞などと同様、脳へと向かう血管のどこかに動脈瘤が発症し、その部分にできた血栓が破綻し血管中を流れて狭くなった部分で詰まることで脳梗塞が起こります。また脳内の末梢血管に破綻を来すと、毛細血管は破れてその先への栄養・酸素供給が止まるため、無理に新しい血管(新生血管)を作り栄養・酸素をとどけようとしますが、この新生血管は非常に脆いため、すぐにまた破綻して出血することになります。こうして障害された脳細胞は、心筋と同様、二度と元にもどることはありません。脳内で失われた機能を代替しようとする動きはありますが、完全に代替することは不可能です。
末梢動脈性疾患(閉塞性動脈硬化症)
糖尿病によって進行する動脈硬化は、下肢を流れる長い血管にも及びます。下肢では太い大腿動脈から膝下の動脈に枝分かれし、さらに足の甲や足裏、足指に至る細い血管へと繋がる中で障害が起こると、足のしびれや痛みが現れ、だんだん歩行も困難になり、止まってしばらく休まないと歩き続けることができない間欠性跛行などの症状が現れ、遂には足への血行が失われて、その先が壊死を起こして切断に至るようなケースまであります。閉塞性動脈硬化症が重症化することを防ぐために、足の動脈硬化の状態を計ることができるABI検査(上腕と足首の血圧の差を計る検査)を定期的に受診することが推奨されています。
細小血管障害
細小血管とは、末梢の毛細血管のことです。糖尿病による血管障害によって眼の網膜にある毛細血管が障害されておこる「糖尿病性網膜症」、腎臓で血液を濾過して尿をつくる糸状体へ集まる毛細血管が障害されて起こる「糖尿病性腎症」、四肢の末梢血管が障害されておこる「糖尿病性神経障害」の三大合併症をあらわしています。
糖尿病性網膜症
網膜はデジタルカメラで言えば、CCDなどの撮像素子と言える部分で、網膜に集められた光情報を電気信号に換えて脳へと送るための視細胞、視神経が集まっており、その活動を維持するために毛細血管が集中しています。糖尿病によってこの毛細血管に破綻を来すと、出血が起こって網膜への栄養・酸素補給が破綻するため、身体はその代替となる新しい血管(新生血管)を大量に作ります。新生血管は非常にもろく、結局のところまた破綻し、視細胞や視神経が障害されていきます。放置すると最悪の場合、失明に至ることもあり、後天的失明原因では常に上位に数えられる重大な合併症です。
糖尿病性神経障害
末梢の血管が糖尿病によって障害されることによって、血管の近辺にある末梢の神経にも障害が及ぶことになります。特に下肢の先端、足指で生じることが多く、初期はしびれや冷えといった症状から始まります。また、神経障害によって痛みを感じられなくなると、傷に気づかず放置してしまうケースがあります。糖尿病によって感染症を引き起こしやすい体質になっているため、すぐに化膿し、そのまま組織の壊死にもつながり、最悪の場合、四肢を切断しなければならないような事態が生じることもあります。また性器周辺で起こることで男性の場合は勃起障害(ED)などが起こることもあります。その他、消化器で神経障害がおこることで胃腸症状、皮膚の近辺では発汗障害などといった実に様々な症状が現れます。
糖尿病性腎症
腎臓の糸球体という部分は、血管から不要物を濾過し、尿に混ぜて排出する働きをしています。そのため、この部分には微細な血管がたくさんあつまっています。糖尿病によってここに集まっている血管が障害されると、血中の不純物の濾過がうまくいかなくなり、身体に尿毒が溜まっていくことや、余分な水分の排泄ができずに身体に水分が溜まってしまうような状態が起こります。これによって、全身の倦怠感、吐き気や嘔吐といった消化器症状などが現れ、最終的には透析をしなければ尿毒が溜まって生命に危険が及ぶことにもなります。
糖尿病足病変
糖尿病による血管障害は、心臓から一番遠い下肢において顕著に現れやすいことがわかっています。下肢の血管に障害が起こることで、毛細血管の破綻によるむくみや神経障害が起こりやすくなり、神経鈍麻によって傷を負っても気づきにくくなり、免疫力の低下により感染リスクが高まると、下肢の組織に炎症、びらん、潰瘍がおこりやすくなったり、細菌感染のリスクが高まったりします。それにより最悪の場合、下肢組織が壊死し、その部分を切断せざるを得なくなることもあります。このような、糖尿病による下肢の症状を総称して糖尿病足病変と言います。糖尿病や高血糖のおそれがある方は、常日頃から足の状態をしっかりとチェックしておくことが大切です。
隠れ糖尿病(食後高血糖)
隠れ糖尿病とは正式な病名ではありませんが、健康診断などで空腹時血糖値を計測しても異常が発見されないのに、食後血糖値を計測すると異常に高い数値を示すタイプの糖尿病、またはその予備軍のことです。健康診断時に発見されにくいため、気づかないうちに進行させてしまうことがあり、注意が必要な病態です。
糖尿病の診断基準
空腹時血糖値、随時血糖値(食後血糖値)、75gブドウ糖負荷試験の2時間後値の3つの数値のどれかが以下に当てはまった時、糖尿病型との診断になります。別の日に同様の検査を行い、2回以上この規準の異常値が確認されると糖尿病と診断されます。
| 血糖値検査方法 | 数値(単位はmg/dL) |
|---|---|
| 空腹時血糖 | 126以上 |
| 随時(食後)血糖値 | 200以上 |
| 75gブドウ糖負荷試験2時間後※ | 200以上 |
※75gブドウ糖負荷試験は、まず空腹時血糖値を計測し、75gのブドウ糖を服用1時間後、2時間後の血糖値を計測する検査です。
ただし、各検査の糖尿病型の数値が2回計測されない場合でも、口渇、多飲多尿、体重減少といった典型的な糖尿病の症状が見られる場合や、HbA1c(ヘモグロビンA1c)の結果が6.5%以上であった場合、糖尿病網膜症の合併症があるといった場合には糖尿病と診断できます。
なおHbA1cとは、血中のヘモグロビンと結びついたブドウ糖の割合を測る検査で、1~2ヶ月間の血糖値の平均を食事と関係なく確認することができる検査です。
このような基準値から、隠れ糖尿病の可能性がある場合は、随時血糖値とHbA1を定期的に計測し、異常値が発見された場合は75gブドウ糖負荷試験を実施する必要があります。
以下に当てはまる方は
「隠れ糖尿病」かもしれません
隠れ糖尿病は、見つかりにくく知らない間に重症化してしまうリスクがあります。隠れ糖尿病が見つかる経緯としては以下のようなパターンがありますので、サインを見落とさないようにしてください。
- 食後血糖値の測定が140mg/dL以上になった
- 尿検査で尿糖を指摘された
- 血液検査をしたらHbA1cの値が6%を超えていた
- 空腹時血糖値が100mg/dLを超えていた
※100~109mg/dL程度あると、食後の血糖値スパイクの可能性が高まります
いずれの場合でも、正常範囲かまたは要注意程度の数値範囲ですが、上述のような理由で、食後に血糖値が高値になっている可能性が高いことを示しています。こうした条件に1つでも当てはまる場合は、1度専門医に相談し、75gブドウ糖負荷試験などの専門的検査を受けてご自身の血糖値の状態をはっきりとさせておいたほうが良いでしょう。
ブドウ糖負荷試験が推奨される方
1.強く推奨される場合
(現在糖尿病の疑いあり)
| 検査の種類 | 数値 |
|---|---|
| 空腹時血糖 | 100~125mg/dLの範囲 |
| 随時(食後)血糖値 | 140~199mg/dLの範囲 |
| HbA1c | 6.0~6.4%の範囲 |
2.行うことが望ましい場合
(将来糖尿病を発症するリスクが高い)
| 検査の種類 | 数値 |
|---|---|
| 空腹時血糖 | 100~125mg/dLの範囲 |
| HbA1c | 5.6~5.9%の範囲 若しくは、糖尿病の家族歴や肥満症のある方 |
なお、これらの検査を行い、糖尿病と診断されたら速やかに治療を開始する必要があります。また、境界型との診断であった場合も、放置せず生活習慣の改善などの指導を受けることを強くお勧めします。
糖尿病の種類
糖尿病は1型と2型に大別されており、罹りやすい年齢層が異なり、病態や治療法などは共通する部分もありますが、初期治療などは大きく異なっています。世界的に糖尿病患者のほとんどは2型で、日本でも95%が2型で占められています。1型、2型以外には妊娠糖尿病、薬物などによる2次性糖尿病があります。
2型糖尿病
2型糖尿病とは
 2型糖尿病はほとんどが生活習慣の乱れから発症するもので、生活習慣病の代表的な物に数えられています。糖尿病罹患者のうち95%はこの2型糖尿病の患者さんで、一般的には中高年に多い病気ですが、近年では食生活の変化などから若年層でも発症が増えています。初期には目立った自覚症状があまり現れず、放置してしまうと様々な合併症を引き起こし、QOL(生活の質)が大きく低下することになりますので、健康診断などで血糖値の異常を指摘されたら、必ず受診して生活習慣のコントロールに取り組んでください。
2型糖尿病はほとんどが生活習慣の乱れから発症するもので、生活習慣病の代表的な物に数えられています。糖尿病罹患者のうち95%はこの2型糖尿病の患者さんで、一般的には中高年に多い病気ですが、近年では食生活の変化などから若年層でも発症が増えています。初期には目立った自覚症状があまり現れず、放置してしまうと様々な合併症を引き起こし、QOL(生活の質)が大きく低下することになりますので、健康診断などで血糖値の異常を指摘されたら、必ず受診して生活習慣のコントロールに取り組んでください。
2型糖尿病の原因
遺伝的な要因に加えて高カロリー食や炭水化物に偏った食習慣、運動不足、睡眠習慣の異常などのほか、喫煙習慣などの嗜好も加わった生活習慣の乱れが引き金となって、インスリンの分泌が低下したりうまく働けなくなったりしてしまうことが原因です。膵島のβ細胞でインスリンは多少なりとも産生されている状態です。
2型糖尿病の症状
初期の段階では目立った自覚症状はありませんが、以下のような兆しが見られることがあります。ただし、全く症状が現れないまま進行してしまう例も珍しくありません。
- 全身の疲労感
- 手足(特に末端の指など)の感覚が鈍くなる
- 手足の末端に刺すような痛みが走ることがある
- 風邪などの感染症に罹りやすい
- 傷ができると治りにくい、膿みやすい
- 口が渇きやすく、尿量、尿の回数が増える
- 空腹を感じ安い
- かすみ目
- 男性機能の低下(勃起不全等)
など
治療
2型糖尿病では、基本的には食事療法や運動療法を中心とした生活習慣の改善で血糖値をコントロールすることが中心となります。
それだけでは結果が得られない場合、血糖をコントロールする薬やインスリンの働きを良くするような薬で薬物療法を検討します。
食事療法
食事療法では、糖質制限と高脂質食、高カロリー食など食生活の偏りを正しながら、バランスの良い食事内容と、早食い、大食い、寝る前の食事などを避けた正しい食事方法を目指して、患者さんそれぞれ体力や体質、病気の進行度に合わせた食事を指導していくことになります。
運動療法
適切な運動を行い、脂肪を減らし筋肉を増やすことで、蓄積された糖質を燃やし、インスリンも効きやすい身体作りを目指します。激しい運動は必要ありません。ウォーキングやジョギング、エアロビクスなどといった有酸素運動を続けて行くことが大切です。当院では患者さんそれぞれの体調、体力、運動経験などにあわせて内容を調整しながら指導しております。
1型糖尿病
1型糖尿病とは
1型糖尿病は、血糖をコントロールするインスリンというホルモンがまったく、またはほとんど産生されなくなることで起こります。インスリンは膵臓の膵島(ランゲルハンス島)にあるβ細胞によって作られますが、この細胞が障害されてしまうことが原因となります。1型の罹患者数は全体の5%程度と割合としては少ないのですが、我が国ではそれでも21万人もの患者さんが1型糖尿病と闘っています。1型糖尿病は生活習慣病では無く、若い人でも発症し、若い患者さんほど急速に進行する傾向があります。
1型糖尿病の原因
1型糖尿病は、膵島のβ細胞が障害されることでインスリンが産生できなくなってしまうというメカニズムまでは分かっていますが、なぜβ細胞が障害されるのかについては現在のところ解明されていません。ただし、大きな要因の1つとして遺伝的要因、もう1つとしては何らかの感染症などをきっかけとする自己免疫によってβ細胞が攻撃されることにあると考えられています。
1型糖尿病の種類
1型糖尿病は、自己免疫に関係してβ細胞が障害されていく進行性の病気です。病気の深刻速度によって「劇症1型糖尿病」「急性発症1型糖尿病」「緩徐進行1型糖尿病」に分類されていますが、最終的にはインスリンはまったく分泌できなくなってしまいますので、様々な合併症を避けるため適切な治療を続ける必要があります。
劇症1型糖尿病
一般的なウイルス感染などによって作られた抗ウイルス免疫が膵島の細胞を攻撃してしまうことで発症するのではないかと考えられています。ただし、血液検査では自己免疫抗体である抗GAD抗体やICA抗体(膵島細胞質抗体)はほとんど見つかりません。進行スピードは非常に早く、1週間程度するとインスリンがほとんど産生されなくなり、血中にケトン体が増えるケトーシスやケトン体のために血液が酸性になってしまうケトアシドーシスを起こす可能性もありますので、早急にインスリンを補充することが大切です。症例は稀で、日本では5000~7000人程度と考えられており、国の難病に指定されています。
急性発症1型糖尿病
発症してから数ヶ月でインスリンがほとんど産生されなくなってしまうのが急性発症1型糖尿病で、自己免疫が関係して膵島のβ細胞を破壊してしまう自己免疫性と、原因が不明の特発性の2つのタイプに分けられます。ほとんどの場合、血液検査で膵島関連自己抗体である抗GAD抗体、ICA抗体などが見つかります。治療途中に一時的に快方に向かうこともありますが、継続的にインスリン治療が必要となる病気で、発症のピークは思春期頃にあります。
緩徐進行1型糖尿病
緩徐進行1型糖尿病はゆっくりと進行するタイプの1型糖尿病で、診断直後はインスリン治療が必要のない程度ですが、数ヶ月後ぐらいからインスリン治療が必須となってきます。膵島関連抗体の抗GAD抗体、ICA抗体などは陽性で、それによって2型糖尿病との鑑別が可能です。治療としてはインスリン治療も必要ですが、β細胞を保護する薬物治療も同時に行います。
1型糖尿病の症状
代表的な症状は以下の通りですが、特に口渇、多飲多尿、体重減少が見られることが多くなっています。
- 口渇(喉が渇く)
- 多飲(大量に水分を摂る)、多尿(尿量が多い)
- 体重減少(エネルギーが蓄積できなくなるため)
- 風邪症状(抵抗力の低下)
- 全身倦怠感(エネルギー蓄積の不良)
- 悪心・嘔吐
- 胃腸症状
- 夜尿(小児の場合)
など
病気が進行して、インスリンがまったく産生されなくなってしまうと、血中に通常ほとんど存在しないケトン体という物質が増えてしまうケトーシスや、ケトン体のために血液が酸性になってしまうケトアシドーシスを起こし、意識レベルの低下など危険な症状が現れることもあります。
治療
1型糖尿病は、どのタイプでもほとんどがインスリンの自己注射による治療となります。その他にも、2型糖尿病の治療薬が有効なケースもあり、また例は少ないとはいえ膵臓移植や膵島移植、人工膵島などの治療も近年では研究されています。
1型糖尿病であっても状況によっては運動・食事療法が有効になることもあります。
薬物療法
インスリンを供給し続ける必要があるため、治療の基本としては、インスリン自己注射になります。一般的には自分で注射しやすい、ペン型の注射器を使用し、患者さんの状態に合わせて効果が異なるペン型の注射器を選択させていただきます。
ただし、1型糖尿病の場合でも内服薬による治療を行うことができる可能性もあります。保険適用の治療としてはαグルコシダーゼ阻害薬があり、その他にも徐々に選択肢が拡がりつつあります。
決まった時間に注射する
「持効型インスリン」
1日のうちの決まった時間に1~2回自己注射を行います。これは膵島からのインスリンの基礎的な分泌を補うためのもので、持効型インスリンと言い、効果がある程度持続するものです。
食前に注射する「速効型インスリン」や「超速効型のインスリン」
主に、食後の血糖値が急上昇しその後急降下することで起こる血糖値スパイクを予防するためのインスリン注射です。食前に速やかに効果を得ることができる速効型や超速効型のインスリンがあります。患者さんの状態に応じて選択します。
インスリンを自動投与できる
「インスリンポンプ療法」
インスリンポンプ療法の場合は、身体にとりつけたカニューレ(注入口)と繋げたハンディなポンプ装置を衣服などに着けて暮らすことになります。ここから超速効型や速効型のインスリンを継続的に投与することで、基礎と追加の両方をまかなうことができます。
身体に注射針を刺すという行動は、多くの方にためらいがあると思います。そのため、当院では、インスリン治療を始める際に、丁寧に使い方やタイミングなどを説明しておりますのでご安心ください。
食事療法
1型糖尿病の場合、2型糖尿病のような食事制限は特にありません。しかし、追加インスリンを投与するからといって、食後血糖値の急激な上昇は避けるようにすべきでしょう。食後血糖値の上昇が多い食物は、炭水化物や糖分ですから、これらを減らし、良質のたんぱく質や食物繊維を増やすとよいでしょう。
発症当初はインスリン不足によって体重減少が見られますが、治療が進むにつれて体重は増える傾向があります。あまり体重が増えすぎてしまうような場合はカロリー計算に基づいて食事療法を行うこともあります。
運動療法
適切な運動を行うことで、脂肪が燃焼し、筋肉量が増えてくることで、インスリンの投与の効果が上がります。そのため運動は積極的に行うようにお勧めしています。当院では、患者さんそれぞれの身体の状態やこれまでの生活状態にあわせて適切な運動療法のメニューをご紹介しております。
妊娠糖尿病・糖尿病合併症妊娠
妊娠糖尿病とは
 女性は妊娠中、身体の仕組みによって様々な体調変化がみられます。なかでも妊娠を契機として糖尿病を発症するケースは多く、全妊婦さんの7~9%程度に上るという報告もあります。このように妊娠中に初めて発見された糖代謝異常を妊娠糖尿病と言います。
女性は妊娠中、身体の仕組みによって様々な体調変化がみられます。なかでも妊娠を契機として糖尿病を発症するケースは多く、全妊婦さんの7~9%程度に上るという報告もあります。このように妊娠中に初めて発見された糖代謝異常を妊娠糖尿病と言います。
放置すると胎児への影響もありますので、しっかりとコントロールしていくことが大切です。なお、妊娠前から糖尿病や糖代謝異常と診断されている場合は、糖尿病合併症妊娠となり妊娠糖尿病には含まれません。
妊娠糖尿病の原因
妊娠糖尿病は、普段からインスリンの働きが弱めの方が妊娠した場合に多く発症すると考えられています。
妊娠すると、赤ちゃんに栄養を届けるための胎盤ができますが、胎盤で分泌されるホルモンの中にインスリンの働きを弱めるものがあり、その影響によってインスリンが十分に働けなくなり、糖代謝異常を起こすことが分かっています。また、インスリンが働きにくい体質には遺伝的要因も関わっている他、過去の巨大児出産や流産、早産などをした経験との関連、肥満体型などにも関係あると考えられています。
妊娠糖尿病が起こす合併症
母体に起こる合併症
- 妊娠高血圧症候群(妊娠後期の高血圧と尿たんぱく)
- 帝王切開リスクの上昇
- 羊水の異常増加
- 肩甲難産(胎児の頭が出た後、肩がひっかかって分娩できない状態、巨大児などで多い95%はこの2型糖尿病)
- 易感染症状態
- 網膜症や腎症を合併や悪化
など
胎児に起こる合併症
- 流産
- 巨大児
- 心臓肥大
- 形態異常
- 新生児期の低血糖
- 新生児期の血液異常、呼吸異常
- ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カリウム等体内の電解質異常
- 新生児期の高ビルビリン血症(黄疸)
- 子宮内胎児死亡、出産時の死亡リスク上昇
など
その他、発育が遅い、将来的に肥満になりやすい、内臓脂肪型肥満になる確率が高いなどの指摘もあります。
診断方法
早期の妊婦検査の際に、随時血糖値を測定し、高値を示した時にはブドウ糖負荷試験を実施し、以下の条件のどれか1つでも当てはまることがあれば妊娠糖尿病の診断となります。
ただし、インスリンの働きは妊娠が進むにつれて弱くなりますので、早期検査で陰性の場合も、中期、後期にそれぞれ血糖値検査を実施して確認することになります。
| ブドウ糖負荷検査の結果 | 数値(単位はmg/dL) |
|---|---|
| 空腹時血糖 | 92以上 |
| 1時間後の血糖値 | 180以上 |
| 2時間後の血糖値 | 153以上 |
治療
食事療法による血糖値コントロールを基本としますが、それだけではうまくコントロールできない場合は、血糖値を抑える薬などは胎児に影響があり服用できないため、インスリン自己注射を行うことになります。
食事療法
お腹の赤ちゃんの分の栄養も摂る必要があるため、その分カロリー制限をしにくいところがあります。そのため、1回の食事量を少し減らして、1日に食べる回数を増やすという方法が有効と考えられています。具体的には朝食、10時のおやつ、昼食、3時のおやつ、夕食、夜食というように分割して食事を摂ります。その分1回の食事量は通常の4~6割程度に留めると良いでしょう。当院では、それぞれの妊婦さんの状態にあわせた食事療法の指導なども行っています。
インスリン療法
血糖値を下げる内服薬などは、胎児への影響がありますが、インスリンは体内由来のホルモンですから、インスリン療法であれば胎児への影響はありません。基本的には自己注射での治療となります。
妊娠糖尿病は治る?
なお、妊娠糖尿病はほとんどの場合、出産などで胎盤が体外に出されるといったん正常値に戻ります。ただし将来的に2型糖尿病を発症するケースが多いとの報告もあり、継続的に血糖値管理を行うことをお勧めします。