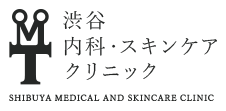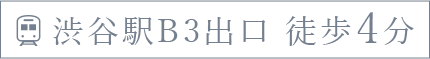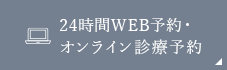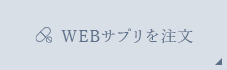むくみとは
 むくみとは、何らかの原因によって皮膚に過剰な水分が蓄積した状態です。むくみは顔から足の先までのあらゆる場所で発生しますが、特に足に多く見られる特徴があります。足は心臓から最も遠くに位置する上、常に重力の影響を受けるために血液が蓄積し、むくみ症状を起こしやすくなります。また、足の血液を心臓に戻す役割を担うふくらはぎの筋肉の働きが加齢や運動不足などによって低下したり、血液の逆流を防ぐための足の静脈の弁の働きが低下することも、むくみを引き起こす原因となり得ます。
むくみとは、何らかの原因によって皮膚に過剰な水分が蓄積した状態です。むくみは顔から足の先までのあらゆる場所で発生しますが、特に足に多く見られる特徴があります。足は心臓から最も遠くに位置する上、常に重力の影響を受けるために血液が蓄積し、むくみ症状を起こしやすくなります。また、足の血液を心臓に戻す役割を担うふくらはぎの筋肉の働きが加齢や運動不足などによって低下したり、血液の逆流を防ぐための足の静脈の弁の働きが低下することも、むくみを引き起こす原因となり得ます。
むくみの原因
むくみの原因には様々なパターンが考えられますが、主に生活習慣が原因のものと病気が関与しているものの2種類に分類されます。
長時間同じ姿勢を続ける
長時間のデスクワークや立ち仕事などによって、ふくらはぎの筋収縮が減り、足の血液を心臓に戻す役割のあるふくらはぎのポンプ機能が低下します。それによって足が鬱血し、むくみを引き起こします。また、このような生活習慣を長期間継続すると下肢静脈瘤を引き起こす恐れもあるため、注意が必要です。
運動不足
慢性的な運動不足は、ふくらはぎの筋力を低下させます。それにより、ふくらはぎのポンプ機能が低下して足の血液を心臓に戻す力が弱まり、足が鬱血してむくみを引き起こします。
ダイエット
ダイエットによって過度な食事制限を行うと、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足して足の筋力を低下させます。それにより、血液を心臓に送り出す機能が低下してむくみを引き起こします。
過剰な塩分のとり過ぎ
 偏った食事習慣などによって塩分を過剰に摂取すると、体内の塩分濃度を一定に保つために体が水分を多く蓄積するようになり、むくみを引き起こします。
偏った食事習慣などによって塩分を過剰に摂取すると、体内の塩分濃度を一定に保つために体が水分を多く蓄積するようになり、むくみを引き起こします。
ビタミン、ミネラル、
タンバク質の不足
ビタミンやミネラル、タンパク質などの栄養素は、身体の働きを正常に保つ役割を担っています。これらが慢性的に不足していると、様々な組織や細胞の働きに異常が生じ、塩分や水分が体内に蓄積しやすくなってむくみを引き起こします。
アルコールの過剰摂取
 過度な飲酒をすると、過剰になったアルコールを分解するために多くの水分が使われて血液濃度が上昇します。この上昇した血液濃度を正常に戻すために血管内に水分が蓄積されるようになり、むくみを引き起こします。
過度な飲酒をすると、過剰になったアルコールを分解するために多くの水分が使われて血液濃度が上昇します。この上昇した血液濃度を正常に戻すために血管内に水分が蓄積されるようになり、むくみを引き起こします。
体温調節不足
デスクワークなどによってエアコンの効いた屋内に長時間滞在すると、自律神経のバランスが乱れて体温調節機能が低下し、体内の水分代謝が異常を起こしてむくみを引き起こします。
冷え
運動不足などが原因で身体が血行不良に陥ると、体内の余分な水分や老廃物を上手に排出できなくなって冷えやむくみなどの症状を引き起こします。
女性特有のむくみ
 一般的に男性より女性の方がむくみを起こしやすい傾向があります。女性がむくみを起こしやすい主な原因は、男性に比べて筋肉量が低いことやホルモンバランスの乱れを起こしやすいことが考えられます。特に生理前は黄体ホルモンを過剰に分泌するため、体内の水分量が上昇してむくみを引き起こします。また妊娠時には、多くの水分を体内に蓄積するためにむくみを起こしやすく、妊娠中の女性の約30%がむくみを起こしているという報告もあります。
一般的に男性より女性の方がむくみを起こしやすい傾向があります。女性がむくみを起こしやすい主な原因は、男性に比べて筋肉量が低いことやホルモンバランスの乱れを起こしやすいことが考えられます。特に生理前は黄体ホルモンを過剰に分泌するため、体内の水分量が上昇してむくみを引き起こします。また妊娠時には、多くの水分を体内に蓄積するためにむくみを起こしやすく、妊娠中の女性の約30%がむくみを起こしているという報告もあります。
年代別のむくみの原因と対処法
20代のむくみ
20代では、特に女性に多く見られます。長時間の立ち仕事やデスクワーク、運動不足などが原因となることがあります。また、下肢静脈瘤や好酸球性血管性浮腫といった病気が隠れていることも。早めに気づき、生活習慣の見直しや適切な対策をとることが大切です。
30代のむくみ
年齢を重ねるとリンパの流れが悪くなり、むくみやすくなっていきます。加えて、生理前、妊娠中、更年期に向けてのホルモンバランスの変化も影響します。身体の変化を意識し、無理のない範囲で運動やセルフケアを取り入れるようにしましょう。
40代のむくみ
更年期が始まる時期であり、女性ホルモン(特にエストロゲン)の減少や自律神経の乱れが、むくみの原因となることがあります。また、筋力の低下や血流の悪化も関係します。仕事や家庭で忙しい時期ですが、適度な休息とストレスケアを心がけることが大切です。
50代のむくみ
更年期や加齢によりホルモンバランスが崩れ、筋力も低下してきます。この年代では、慢性的なむくみが見られることもあり、心臓や腎臓、肝臓などの内臓の不調が隠れている可能性もあります。健康診断で異常を指摘されたことがある方は、早めに医師へ相談しましょう。
60代のむくみ
加齢による心肺機能や筋力の低下、長時間同じ姿勢でいること、塩分の取りすぎなどがむくみを引き起こしやすくなります。高齢者に多く見られる「慢性下肢浮腫」は、心臓病や腎臓病などのサインである場合もあるため注意が必要です。足を高くして休む、やさしくマッサージを行う、塩分を控えた食事を心がけるなどのセルフケアに加えて、気になる症状があれば医療機関を受診しましょう。
病気が原因で起こるむくみ
生活習慣が原因のむくみの場合は1日〜数日間で自然に治まることが多いですが、数日経過しても症状が治まらない場合や指で皮膚表面に凹みが生じる場合は、何らかの病気が関与している可能性があります。中には心不全などの緊急かつ重篤な病気の可能性もあるため、注意が必要です。
下記の症状に該当する場合には、できるだけ早めに当院までご相談ください。
- 1日中むくみ症状が続く
- 数日経過してもむくみ症状が改善しない
- 顔やまぶたにむくみが生じている
- むくみとともに痛みやだるさを伴う
- むくみとともに疲れを感じやすい
- むくみとともに頻尿・排尿困難などの症状を伴っている
- コブのように足の血管が浮き出ている
- 階段の上り下りなどちょっとした運動で息切れする
- 急激に体重が増加している
心臓の障害によるむくみ
 心不全などの病気によって心臓に何らかの異常が生じると、血液を全身に送り出すポンプ機能が低下して血流が滞り、むくみ症状が現れることがあります。また、発症すると、胸の痛みや息切れ、動悸、咳などの症状が現れます。
心不全などの病気によって心臓に何らかの異常が生じると、血液を全身に送り出すポンプ機能が低下して血流が滞り、むくみ症状が現れることがあります。また、発症すると、胸の痛みや息切れ、動悸、咳などの症状が現れます。
心不全の場合には緊急性を伴うため、気になる症状が現れた際には速やかに当院までご相談ください。
肝臓や腎臓の障害によるむくみ
検診等の血液検査で血中のアルブミン量の低下を指摘された場合には、肝臓や腎臓が何らかの障害を起こしている恐れがあります。肝臓や腎臓に異常が生じると、血液の水分調節機能が低下してむくみを引き起こすことがあります。浮腫みと併せて、尿が出ない、少なくなった・おなかや背中の痛みなどの症状が生じる場合は腎臓疾患が潜んでいる可能性があります。また、肝臓疾患では、皮膚の黄染や乾燥、腹水(お腹のむくみ)や腹部の張りを感じるなどの症状が現れます。
リンパ浮腫
(当院では治療対象外)
何らかの原因によってリンパ管に浮腫が生じると、リンパ液の流れが阻害されてむくみ症状を引き起こすことがあります。リンパ液の流れが滞る主な原因としては、リンパ節切除や放射線治療によるリンパ節の損傷が挙げられます。また、原因が分からない場合は特発性リンパ浮腫と診断されます。リンパ浮腫は放置すると急性リンパ管炎へと進行したり、蜂窩織炎を併発することもあるため、注意が必要です。
リンパ浮腫は自然治癒することはないため、改善には専門の医療機関で適切な治療を行う必要があります。なお、当院ではリンパ浮腫の治療は行っておりませんので、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
深部静脈血栓症
(エコノミークラス症候群)
深部静脈血栓症とは一般的にエコノミークラス症候群と呼ばれている病気です。主な原因は、長時間のバス・飛行機などの移動やデスクワークなどで同じ態勢を維持することで、足の静脈が鬱血して血栓が生じることなどが挙げられます。また、血流が阻害されることでむくみ症状を引き起こすこともあります。
改善には、こまめに運動してふくらはぎの筋肉を動かすことや、十分な水分補給、弾性ストッキングを履くなどが効果的です。