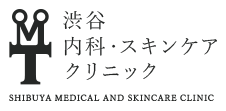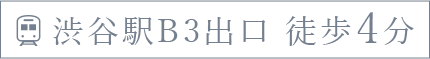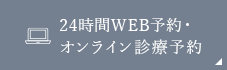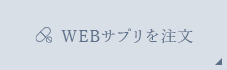当院の腎臓内科のご案内
- 「専門的に相談したいが、透析中心の病院ばかり…」
- 「健診で腎機能が悪いと言われたけれど、どうすればよいかわからない…」
- 「薬だけでなく生活習慣の改善もサポートしてほしい…」
そんなお悩みはありませんか?
腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、自覚症状が出にくい臓器です。気づかないうちに進行し、将来透析が必要になるケースも想定できます。渋谷内科・スキンケアクリニックでは、透析を予防する腎臓内科診療に力を入れています。
当院では腎臓内科専門医が病院レベルの検査を最小限で行い、原因を丁寧に評価。治療と指導を行うとともに、「何を食べれば良いか」に重点を置いた栄養指導や生活習慣のサポートを提供しています。
腎臓病は早期に正しく対策をとることが、将来の透析予防につながります。健診や血液検査で異常を指摘された方、むくみ・足の指圧後の凹み・血圧が上がってきた・疲労感が強い・尿の泡立ち・血尿・頻尿など気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
迷ったときこそ、まずは当院の腎臓内科へ。
- 当院の腎臓内科の特徴
- 腎疾患が潜んでいる可能性がある症状
- 急性腎不全と慢性腎不全
- よくある疾患
- 喉が渇いてからの水分補給は遅い?
脱水症、熱中症の予防と対処法 - 腎臓内科の診察の流れ
- なぜ血液検査・尿検査が必要?!
当院の腎臓内科の特徴
腎臓病を抱える方々に、生涯を通じて寄り添う診療を心がけています
 当院ではネフローゼ症候群や慢性腎炎、多発性嚢胞腎などの腎臓病の検査・診断・治療まで行います。急性期の場合や精密検査などが必要な場合は専門の医療機関へご紹介させていただきます。病状が安定したら、当院でのアフターフォローが可能です。
当院ではネフローゼ症候群や慢性腎炎、多発性嚢胞腎などの腎臓病の検査・診断・治療まで行います。急性期の場合や精密検査などが必要な場合は専門の医療機関へご紹介させていただきます。病状が安定したら、当院でのアフターフォローが可能です。
また、タンパク尿、糖尿病、高血圧、肥満症などの生活習慣病も放置しておくと腎臓病になりますので、すでにこれらの治療をしている方で腎臓の状態が気になる方も当院で検査・治療を並行しておこなえます。将来的な透析のリスクを回避するために、定期的に検診を受け、早期発見・進行予防が大切です。
腎臓内科診療実績
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2023年 | 834件 |
| 2024年 | 1505件 |
腎疾患が潜んでいる
可能性がある症状
下記のような症状は腎臓に負担がかかっているサインです。
だるい・慢性的な疲労感がある
 風邪ではないのに体がだるい、慢性的に疲労感がある場合は、腎臓疾患が潜んでいる可能性があります。日常的なだるさや疲れが気になる場合は、早めに当院を受診してください。
風邪ではないのに体がだるい、慢性的に疲労感がある場合は、腎臓疾患が潜んでいる可能性があります。日常的なだるさや疲れが気になる場合は、早めに当院を受診してください。
高血圧を指摘された
腎臓の機能が低下すると、塩分や水分を排泄する働きが低下し、心臓の負担が増え血圧が上昇します。高血圧が続く場合には、腎疾患も疑い早めに受診しましょう。
さらに、血圧が高い状態が続くと腎臓への負担がかかり、さらに腎機能が低下する悪循環を引き起こすので血圧のコントロールは重要です。
顔や手足のむくみがある
むくみが出やすい場所としては、まぶたや顔、手の甲や足のすね・足の甲があります。むくみは妊娠や飲酒などが原因でも見られますが、心当たりがないむくみは腎臓疾患などの病気が潜んでいる可能性があります。
腎臓の機能が低下すると、水分や塩分がうまく排出できずにむくみが発生します。また、普段尿に含まれないタンパク質が血中に溶け出し、むくみを進行させます。またむくみは体表にとどまらず、心臓の周囲や肺、肝臓、胃腸、 肺にも現れます。
特に肺にむくみが生じると、呼吸困難に陥ることがあり非常に危険です。むくみの症状が続く場合は、お早めに当院にご相談ください。
尿量・色の変化した
 何らかの原因で腎機能が低下すると、尿をろ過・濃縮する機能が低下して尿量が増加します。
何らかの原因で腎機能が低下すると、尿をろ過・濃縮する機能が低下して尿量が増加します。
進行すると、尿量はわずかになり尿が排出されなくなることもあります。また、腎臓がんや結石を発症し、尿管や膀胱が閉塞されると尿量が減少することがあります。
健常な方(成人)の1日の尿量は1000~1500mlですが、末期腎臓病患者では乏尿(尿量400mL/日以下)や無尿(尿量100mL/日以下)がみられます。
また、尿が濁っている・尿に浮遊物がある場合には、尿路感染症が疑われます。
さらに、尿が泡立つ、赤い尿の場合は、腎炎など腎臓病が潜んでいる可能性があります。尿の変化は健康状態を示す重要な指標です。気になる症状がある方は、お早めに当院へご相談ください。
健診で尿蛋白(+)を指摘された
尿中にタンパク質が溶け出ている状態をタンパク尿と言い、健康診断では、「尿蛋白(+)」と表記されます。本来腎臓は、余分な水分や老廃物だけをろ過して尿として排出する働きを持っているため、尿中にたんぱく質が出ることはほとんどありません。
しかし、腎炎が生じている場合や、何かしらの原因で腎臓に負荷がかかっている場合には、タンパク尿が生じます。
タンパク尿は、原因疾患によって治療法が異なるために、まずは正確な診断が必要です。たんぱく尿を指摘されたら、放置せずに早めに当院を受診してください。
健診で尿潜血(+)を指摘された
尿中に赤血球が混じっている状態を血尿と言い、一般的に、目視で血尿を確認できる「肉眼的血尿」と、検査紙や顕微鏡などの検査で初めて血尿を確認できる「顕微鏡的血尿」に分けられます。
健康診断ではどちらの血尿も「尿潜血(+)」と表記されます。顕微鏡的血尿は、糸球体腎炎など組織の疾患が多く、肉眼的血尿は、腎臓や膀胱、尿管、尿道に結石や感染症、悪性腫瘍などが考えられます。疲労からの一過性の尿潜血もありますが、尿潜血を指摘されたらすぐ当院までご相談ください。
クレアチニン値が高い/
eGFR値が低いと指摘された
健康診断などの血液検査で、クレアチニンという項目を見かけることがあると思います。
これは筋肉が働いた時にできる老廃物の一種で、健康であればほとんどが尿に混ざって体外に排泄されます。しかし、なんらかの原因で腎機能が低下していると、血中のクレアチニン濃度は高くなります。
一方、腎臓のろ過機能の状態をあらわすのがeGFR(推算糸球体濾過量)という数値です。この数値は一般的には血清クレアチニン値と年齢、性別を用いて算出し、数値が低いほど腎臓の濾過機能が低下していることを示します。
また、細胞活動の廃棄物である尿素が持つ窒素の量を示す血清尿素窒素(BUN)なども同時に確認することで、血液検査によって腎臓の活動の状態を確認しています。
急性腎不全と慢性腎不全
腎不全とは、腎臓の働きが大きく低下し、身体の不要な水分や血中の老廃物や毒物などを濾過し尿として排泄するなどの機能が、正常な腎機能の30%以下にまで低下した状態を指す用語で、その原因は様々です。
腎不全は急性のものと慢性のものに分けられ、急性腎不全は数時間から数日の間に急激に腎機能が低下した状態で、尿量が大幅に低下したり(乏尿)、まったく出なくなったり(無尿)といった症状が現れたりします。
それに対し、慢性腎不全はあまりはっきりした初期症状は現れず、数ヶ月から数年という長い時間をかけてゆっくりと腎機能が低下していくものです。
症状としては、水分が身体に滞留するための浮腫が一般的ですが、その他にも全身のだるさ、疲れやすさ、食欲が出ないといった全身症状や、皮膚の痒み、夜間頻尿などが現れることもあります。
よくある疾患
高血圧性腎臓病
高血圧は腎臓の血管にも動脈硬化を起こして、腎臓のはたらきを弱くしていくため、お薬による適切な血圧管理が必要です。
降圧薬(高血圧のお薬)の種類はたくさんありますが、それぞれ特徴は異なり、一人ひとりに合ったお薬を見つけることが大切です。高血圧治療中の方も自分に合っているかご心配の方は一度当院にご相談ください。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は糖尿病が原因で腎臓の機能が低下した症状をいい、人工透析の原因の第1位です。
初期症状は尿中にタンパクが出るのみで、進行すると尿中に大量のタンパクが出て、むくみなどの症状がでます。
さらに進行すると体内に老廃物や水分が溜まり、腎不全や尿毒症を起こします。糖尿病性腎症の方は神経症状や網膜症を合併していることが多いです。食事・運動管理だけでなく血圧、血糖管理が重要です。
腎炎(IgA腎症など)、
ネフローゼ症候群
腎臓の糸球体という構造に炎症をおこす病気をいい、主に健診で血尿やタンパク尿を指摘されて発見されます。尿中に大量のタンパクがでて、血管内のタンパクが失われてしまう状態をネフローゼ症候群と呼びます。
ネフローゼ症候群では腎不全や心不全、脳梗塞、心筋梗塞、感染症などの合併リスクが上がります。原因はさまざまなため、基幹病院と連携して対応いたします。診断がつくことで、適切な治療法が選択できますので当院でのアフターフォローが可能です。
急性腎障害
数時間から数日のうちに急激に腎臓の機能が低下する状態を言います。尿から老廃物を排泄できなくなったり、体内の水分や塩分量などを調節することができなくなります。
脱水や出血による腎臓への血流低下(腎前性)や、腎臓の炎症など(腎性)、尿路系の閉塞など(腎後性)が原因となります。
急性腎障害は高齢者や慢性腎臓病の方に起こりやすく、早急に原因を突き止め治療を行えば、腎機能の回復が見込めますが、慢性腎臓病や末期腎不全に移行する場合も多くありますので注意が必要です。
腎性貧血
腎臓は赤血球を作るはたらきを助けるため、エリスロポエチンというホルモンを分泌します。
腎臓の機能が低下すると、このエリスロポエチンの分泌が減少し、赤血球を作る能力が低下するため貧血になります。この貧血を腎性貧血といいます。
腎性貧血の治療には鉄欠乏性貧血のように鉄剤投与のみでは改善しません。エリスロポエチンの分泌不足を補う注射薬や、体内のエリスロポエチン産生を促す内服薬などによる治療が必要です。
薬剤性腎障害
腎臓の障害は薬によって起こることもあります。代表的なお薬として鎮痛薬として用いられるロキソニンやボルタレンなどのNSAIDsや抗菌薬、高血圧のお薬などがあります。治療は原因となるお薬を突き止めて可能な限り早期に中止あるいは減量することです。
多発性のう胞腎
両側の腎臓に液体の詰まった嚢胞という袋がたくさん作られ、正常な部分を破壊していく遺伝性の腎臓病です。近年お薬の開発も進んでおり、進行が抑えられるようになりました。心当たりのある方はお早めにご相談ください。早期に対応することで、透析になる前に悪化を予防しましょう。
喉が渇いてからの
水分補給は遅い?
脱水症、熱中症の
予防と対処法
 脱水症は身体に必要な水分が大幅に不足してしまうことで、脱水症が進むことで、体温調節機能がうまく働かなくなると熱中症を起こしやすくなります。
脱水症は身体に必要な水分が大幅に不足してしまうことで、脱水症が進むことで、体温調節機能がうまく働かなくなると熱中症を起こしやすくなります。
熱中症や脱水症は何も酷暑の時だけに起こるわけではなく、湿度が高い状態でも起こります。
特に高齢者や子どもの場合、水分が不足しているという状態に気づきにくいこともありますので「のどが乾いた」といった異常を感じる前に適切に水分を補給する習慣をつけることも大切です。
また、電気代が気になるなどからエアコンをつけることに抵抗を感じる方もありますが、そのため就寝中に熱中症を起こすこともあります。室温の適切なコントロールも心がけるようにしましょう。
以下のような症状が出たら
早めに受診しましょう
- めまい、ふらつき
- 吐き気や嘔吐
- 普段経験したことのない頭痛
- 悪心(吐き気や気持悪さ)
- 体温の上昇
- 大汗が出る、またはまったく汗が出ない
- 失神、体温の上昇による熱失神
- けいれんや発熱による熱性けいれん
- 高体温による熱疲労
- 意識レベルの低下
など
腎臓内科の診察の流れ
1診察
 問診表をもとに医師が診察します。
問診表をもとに医師が診察します。
2検査
必要に応じて検査(採血・尿検査・腎臓エコー検査※など)をおこないます。腎臓の評価と診断を適切におこなうため、一般の検査項目のほかに多数の項目が必要となります。ご不安な点がございましたら医師に直接ご相談ください。
3検査結果説明
検査結果がわかるものに関しては、医師から結果説明をいたします。検査項目によっては数日かかるため、後日再来院していただく場合がございます。
4診断・治療
診察と検査結果から適切な診断と治療についてご説明いたします。より専門性の高い検査や治療が必要となった場合には、各専門の医療機関にご紹介いたします。
病状が安定したら、当院でのアフターフォローが可能です。
※2 腎臓エコー検査は、超音波で内臓の性状を観察する検査です。痛みがなく、放射線による被曝もないので安心です。主に血液検査や尿検査で腎臓の機能の低下がある時、病態を把握するために行われます。診察料を除き、3割負担で1,500~2,000円前後になります。
予防医学検査
ミネラル検査
なぜ血液検査・尿検査が必要?!
血液や尿は、私たちの体の状態をそのまま映し出す“鏡”のようなものです。
自覚症状がなくても、体の中では少しずつ変化が起きていることがあります。
血液検査や尿検査を行うことで、臓器の働きや代謝の状態、炎症や感染の有無などを早い段階で確認することができます。
血液検査では、貧血や感染症、肝臓・腎臓・心臓の機能、血糖やコレステロールなど生活習慣病のリスクを総合的にチェックします。
尿検査では、腎臓や膀胱の異常、体の水分・塩分バランス、糖尿病や肝臓の異常の兆しなどを調べることが可能です。
これらの検査は、病気の早期発見や健康管理、治療中の経過観察に欠かせません。
特に高血圧や糖尿病、脂質異常症などは初期症状が出にくいため、定期的な血液・尿検査が健康維持の大切なポイントになります。
当院では、結果を医師がわかりやすくご説明し、必要に応じて生活習慣の改善や治療につなげます。
「最近少し疲れやすい」「健康診断の結果が気になる」といった方も、どうぞお気軽にご相談ください。
このような方にお勧めしています
- 不規則な生活習慣を送っており、将来が心配
- 身体や心の不調が続いてイライラしたり不安になったりする
- 癌や心疾患、脳疾患などの生活習慣病の家族歴がある
- 自身の身体に今どのような栄養素が必要なのか知りたい
- きちんとバランス良く食べることができているかが心配
- 加工食品
- 自身の身体がどのような状態なのかを把握しておきたい
- 知らない間に排ガスや仕事環境などで身体に毒素が溜まっていないか心配
- 内臓や肌、骨などの老化が心配
- 体調がずっと良くないけれど、定期健診では異常が無いといわれる
- 子どもが欲しい、妊娠したい
- 子どもが正常に発育・発達しているかが不安
- 普段あまり気にしないミネラルなどを正常に摂れているか、どのような働きをしているかを知りたい
など