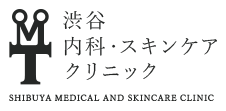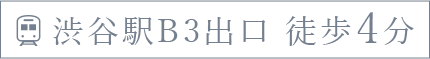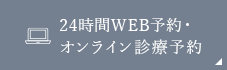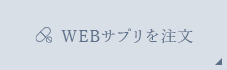- 腎臓にいい食べ物とは
- 腎臓病の方に塩分制限をするのはなぜ?
- 腎臓病の方が果物・野菜を食べるときの
注意点 - 腎臓病の際に食べてはいけない食べ物
(注意が必要な食品) - 腎臓病を悪化させないための
適切なタンパク質の摂り方 - 腎臓を強くする食べ物とは
- 適切な食事療法を受けるには?
腎臓にいい食べ物とは
腎臓の病気を患っている場合には、食事習慣の見直しが病状の改善に有効です。具体的には、塩分の多い食事を控える、野菜や果物、適切なタンパク質の摂取などを行うようにしましょう。また、野菜や果物にはカリウムや食物繊維が豊富に含まれているため、老廃物の排出機能を高めたり高血圧予防にも効果的です。ただし、中等度以上の腎機能障害と診断されている場合にはカリウムの摂取制限が必要なため、担当医の指示に従ってください。その他、白身の魚や豆類などのタンパク質の摂取は腎機能を高める効果が期待できます。ただし、過剰摂取は逆に腎臓への負担を増大させるため、医師のアドバイスに従い適切な量を摂取するよう心がけましょう。
腎臓病の方に
塩分制限をするのはなぜ?
塩分の過剰摂取は腎臓の負担を増大させるだけでなく、高血圧にも繋がり、腎機能の低下を加速させる原因となります。そのため、日々の食事習慣では減塩を心がけましょう。一般的に、1日の適切な塩分摂取量は6〜7gとされているため、この数値を目標に1日の食事を調整しましょう。ただし、高血圧と診断されている場合や浮腫がある場合には、1日5g以下が理想です。
美味しく塩分制限するには?
食事習慣の改善は、調味料の代わりにスパイスやハーブを使う、外食や加工食品を控えるなどが効果的です。また、食品を購入する際には栄養成分表を確認し、塩分量の多いものは控えるようにしましょう。ソーセージや缶詰、塩漬け、スナック菓子などは塩分量が多いため、症状が改善するまでは避けるようにしましょう。ただし、これらはあくまで一般論となります。病状や体質には個人差があるため、具体的な塩分制限の方法に関しては医師や栄養士の指示に従ってください。
塩分を減らすことで
期待できる効果
血圧の管理
過剰な塩分摂取は血圧を上昇させるため、控えるようにしましょう。
腎臓への負担軽減
過剰な塩分摂取は腎臓への負担を増大させます。そのため、塩分を制限することは腎機能の改善に役立ちます。
浮腫の軽減
塩分を過剰に摂取すると、体内に余分な水分が蓄積して浮腫を引き起こします。そのため、塩分を制限することは浮腫の予防に役立ちます。
心血管の健康維持
過剰な塩分摂取は心血管疾患のリスクを高めます。そのため、塩分の制限は心臓や血管の健康維持に効果的です。
ナトリウムとのバランス
塩分にはナトリウムが含まれているため、塩分を制限することで体内のミネラルバランスを適切にコントロールすることができます。
腎臓病の方が果物・
野菜を食べるときの注意点
野菜や果物には、腎機能を改善させるための豊富な栄養素が含まれています。ただし、適切に摂取しないとかえって逆効果になることもあるため、注意が必要です。
果物・野菜の
適正量を知りましょう
 カリウムは腎臓の老廃物排出機能を高める効果が期待できるため、カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂取するようにしましょう。カリウムを含む食材としては、トマト、ほうれん草などの野菜類やオレンジ、バナナ、スイカなどの果物類が挙げられます。ただし、高カリウム血症の状態でカリウムを過剰接種すると重篤な不整脈を引き起こす恐れもあるため、その場合には必ず医師の指示に従って摂取してください。
カリウムは腎臓の老廃物排出機能を高める効果が期待できるため、カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂取するようにしましょう。カリウムを含む食材としては、トマト、ほうれん草などの野菜類やオレンジ、バナナ、スイカなどの果物類が挙げられます。ただし、高カリウム血症の状態でカリウムを過剰接種すると重篤な不整脈を引き起こす恐れもあるため、その場合には必ず医師の指示に従って摂取してください。
リンが多く含まれる野菜は
避けましょう
腎機能が低下している場合には、リンの排出が困難になります。そのため、乳製品やレバー、ナッツなどのリンを多く含む食品の摂取は控えるようにしましょう。
バランスよく摂取しましょう
栄養の摂取はバランスが重要です。偏った食生活は避け、様々な野菜や果物を摂取してビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質などの栄養素をバランス良く取り入れるよう心がけましょう。
腎臓病の際に食べてはいけない
食べ物(注意が必要な食品)
下記はあくまで一般的な目安となります。腎臓病の重症度や患者様の状態によって制限すべき食品には個人差があるため、医師や栄養士に相談しましょう。
高カリウム食品
- トマト
- ほうれん草
- 白菜
- キャベツ
- かぼちゃ
- イモ類
- オレンジ
- キウイ
- バナナ
- スイカ
- さくらんぼ
など
高ナトリウム食品
- 加工食品
- 缶詰
- 調味料
- スナック類
など
高リン食品
- 乳製品
- レバー
- ナッツ
- 種子類
など
糖質の多い食品
- 砂糖
- スイーツ
- 甘い飲み物
など
高たんぱく食品
- 肉
- 卵
- 魚
- 大豆製品
など
腎臓病を悪化させないための
適切なタンパク質の摂り方
タンパク質の摂取は腎臓病の改善に有効です。しかし、適切に摂取しないとかえって病状を悪化させてしまうケースもあるため、注意が必要です。
高品質なタンパク質を選ぶ
 卵や魚、鶏肉などの動物性タンパク質や乳製品は高品質なものを選択することで、腎臓に負担をかけずに栄養を摂ることができます。
卵や魚、鶏肉などの動物性タンパク質や乳製品は高品質なものを選択することで、腎臓に負担をかけずに栄養を摂ることができます。
ただし、動物性タンパク質の摂取量は、1日摂取する全てのタンパク質のうち、50〜60%に抑えるよう調整しましょう。
タンパク質の摂取量を調整する
一般的に中等度以上の腎不全の場合の適切なタンパク質の摂取量は体重1kgあたり0.6~0.8gが理想と言われていますが、病状の進行度合いや体格によって個人差があるため、医師や栄養士の指示のもと、適切な量を摂取するようにしましょう。
タンパク質の分散摂取
タンパク質は1日の食事の中でバランス良く摂取するようにしましょう。1回の食事で多くのタンパク質を摂取するのではなく、1日の中で摂取を複数回に分けることで、腎臓の負担を分散させることができます。
糖質や脂質とのバランスを考える
タンパク質だけでなく糖質や脂質の摂取量も調整してバランスの良い食事を心がけましょう。
栄養士の指導を受ける
腎臓に異常がある場合には、栄養の摂取は自己判断で行うのではなく、栄養士や医師といった専門家の指示に従うようにしましょう。専門家の意見は病状の早期改善に効果的です。
腎臓を強くする食べ物とは
良質な炭水化物
良質な炭水化物はエネルギー源として腎機能の改善に効果的です。野菜や果物、穀物などの炭水化物をバランス良く摂取するようにしましょう。
必須脂肪酸
マグロやサーモンなどから摂れるオメガ3脂肪酸やナッツ類は腎機能の改善に効果的です。
低塩分の食品
塩分の過剰摂取は腎臓の負担を増大させるため、調理の際にはスパイスやハーブを代用するようにしましょう。
抗酸化物質を含む食品
抗酸化物質は、体内の活性酸素を除去して腎臓を保護する効果が期待できます。抗酸化物質は、緑黄色野菜やベリー類に豊富に含まれています。
水分摂取
 水分の摂取は体内に蓄積した老廃物を排出したり腎臓の血流を促進する効果があります。ただし、水分摂取をする際にはアルコールやカフェインを多く含むものは避け、水やハーブティーなどで行うようにしましょう。
水分の摂取は体内に蓄積した老廃物を排出したり腎臓の血流を促進する効果があります。ただし、水分摂取をする際にはアルコールやカフェインを多く含むものは避け、水やハーブティーなどで行うようにしましょう。
腎機能を改善させるための食事の設計は専門知識が必要なため、自己判断で行うのではなく栄養士や医師などの専門家の指示に従うようにしましょう。
適切な食事療法を受けるには?
 腎臓病は、専門的な知識や経験を持った医師や栄養士の治療や管理によって改善効果を最大化させることができます。当院では、日本腎臓学会認定の腎臓専門医が治療を担当しておりますので、何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
腎臓病は、専門的な知識や経験を持った医師や栄養士の治療や管理によって改善効果を最大化させることができます。当院では、日本腎臓学会認定の腎臓専門医が治療を担当しておりますので、何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。