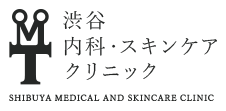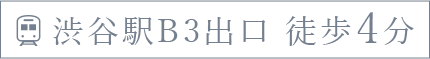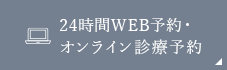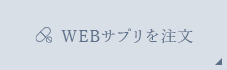腎臓の働きと慢性腎臓病(CKD)について~腎臓内科医がわかりやすく解説します~
腎臓とはどんな臓器?
腎臓は、お腹の奥の背中側に左右1つずつある、握りこぶしほどの大きさの臓器です。形はそら豆に似ています。
主な役割は 血液をきれいにして尿を作ること。体にたまった老廃物や余分な水分を排泄し、体のバランスを整える“浄水場”のような働きをしています。
尿ができる仕組み
血液は腎臓に入ると、まず「糸球体(しきゅうたい)」という細かなフィルターを通ります。ここで不要なものが濾され、「原尿(げんにょう)」と呼ばれる最初の尿ができます。
その後「尿細管(にょうさいかん)」を通る間に、水分や塩分、必要な栄養素が再吸収され、体に残すべきものは戻されます。こうして調整されたものが「最終的な尿」として体外に排泄されます。
この仕組みにより、私たちは 塩分を摂りすぎても、また水分が足りなくても、腎臓が自動的に調節してくれる のです。
腎臓の大切な働き
腎臓は尿を作る以外にも、体を守るさまざまな役割を担っています。
• 血圧をコントロールする
• 赤血球をつくるホルモンを分泌して貧血を防ぐ
• ビタミンDを活性化し、骨を丈夫に保つ
• 体を弱アルカリ性に保ち、酸・塩基のバランスを整える
腎機能を調べる検査(eGFRとは?)
腎臓の働きを評価する指標の一つが GFR(糸球体ろ過量) です。
GFRは腎臓がどのくらい老廃物を排泄できているかを示すもので、血液検査の「クレアチニン値」と年齢・性別をもとに計算される eGFR が一般的に使われています。
• 正常値:70以上
• 60未満が3か月以上続く場合:慢性腎臓病(CKD) と診断されます。
慢性腎臓病(CKD)とは?
慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、次のいずれかに当てはまる状態が3か月以上続くと診断されます。
• 尿検査や血液検査、画像検査などで腎臓に異常がある
• eGFRが60未満である
CKDは進行度に応じてステージに分けられ、ステージが上がるほど腎機能は低下していきます。腎臓は「予備力」があるため、かなり悪くなるまで症状が出にくいことが特徴です。
腎機能低下で現れる症状
腎臓病は“沈黙の病気”と呼ばれ、初期には症状がほとんどありません。
しかし進行してくると、次のような症状が出てきます。
• 夜中に何度もトイレに行く(夜間尿)
• 動悸や息切れ、疲れやすさ(腎性貧血)
• 足のむくみや高血圧
• 手足のしびれや不整脈(高カリウム血症)
• 骨が弱くなる(腎性骨症)
これらは腎臓の働きが落ちてきているサインです。
慢性腎臓病と生活習慣
CKDが進行すると、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクも高まります。
腎臓を守るためには、生活習慣の見直しが欠かせません。
• 塩分を控える(1日6g未満を目安に)
• 適度な運動を続ける
• 禁煙する
• 睡眠を十分にとる
• 糖尿病・高血圧・脂質異常症の治療をしっかり行う
腎臓病の主な種類
腎臓病にはさまざまなタイプがあります。
• 急性糸球体腎炎:風邪のあとに血尿やむくみが出る。入院が必要になることも。
• IgA腎症:血尿や蛋白尿が長期間続く。早期に治療すると進行を抑えられる。
• 急速進行性糸球体腎炎:短期間で腎機能が急低下。透析が必要になることもあるため早急な治療が必要。
• ネフローゼ症候群:尿の泡立ちや全身のむくみ。血液中の蛋白が減少する病気。
• 多発性嚢胞腎(ADPKD):腎臓に多数の嚢胞ができ、腎臓が大きくなっていく遺伝性の疾患。
まとめ
腎臓は私たちの体を支える“影の立役者”です。
悪くなっても症状が出にくいからこそ、健診や尿・血液検査で異常を指摘されたら早めの受診が大切です。
「腎臓は沈黙の臓器」――異常を見逃さず、早期発見・早期治療を心がけましょう。