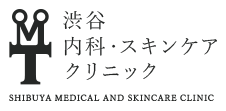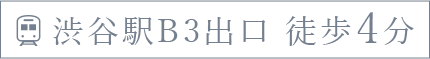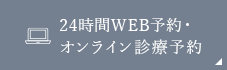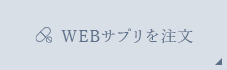高血圧とは
高血圧は、血圧が常に高い状態です。繰り返し測定した結果、正常範囲を超えると診断されます。具体的には、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHgを超える、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHgを超える状態を言います。
自覚症状が少ないため、高血圧の未治療患者数は推定で約2000万人に上ります。環境や生活状況によって高血圧のリスクは変動しますが、早期に発見し治療することが大切です。健康診断での血圧測定が普及していますが、家庭用の血圧計を使うことも推奨されています。家庭用血圧計で血圧が125/75mmHg以上であれば、速やかな受診が勧められます。
高血圧症の代表的な合併症
| 脳疾患 | 脳血管障害(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血) |
|---|---|
| 心疾患 | 冠動脈硬化症、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、うっ血性心不全、心肥大 |
| 腎疾患 | 腎細動脈硬化症、慢性腎不全 |
| 血管障害 | 下肢閉塞性動脈硬化症、眼底出血 |
血圧が上がる原因
血圧が上がる原因として下記が挙げられます。
- 塩分の過剰摂取による血液中の水分量上昇
- 運動不足による塩分排出不足
- 喫煙による一酸化炭素の上昇、血管の収縮
- 肥満によるホルモンや自律神経の乱れ
- ストレスにより血管を収縮させるホルモンが増加
- 加齢による血管の柔軟性の低下
- 遺伝的要素
など
血圧の基準値
 心臓はぎゅっと縮んだ時(収縮期)に血液をどっと送り出し、緩んだ時(拡張期)には戻ってくる血液を取り込みます。血管は柔軟性をもって送り出された血液を受け止め、先に進める役割を果たしています。収縮期には血管にかかる圧力は上がり、拡張期には圧力が下がります。この時血管にかかる圧力を血圧といい、mmHgという単位で表します。
心臓はぎゅっと縮んだ時(収縮期)に血液をどっと送り出し、緩んだ時(拡張期)には戻ってくる血液を取り込みます。血管は柔軟性をもって送り出された血液を受け止め、先に進める役割を果たしています。収縮期には血管にかかる圧力は上がり、拡張期には圧力が下がります。この時血管にかかる圧力を血圧といい、mmHgという単位で表します。
血圧は人によっても、また同じ人でも活動状態によって異なりますが、その人にとってずっと血圧が高い状態が続くと血管がダメージを受けて動脈硬化を起こしやすくなってしまいますので、標準的な血圧にコントロールする必要があります。
血圧のコントロール方法は生活習慣の見直しから薬物療法まで様々なものがありますが、自身に合った方法で焦らず気長に続けていくことが大切です。
また、近年では医師が診察室で測る(診察室血圧)のは参考値程度に留め、自宅で自身が毎日時間を決めてリラックスした状態で計測し、血圧の変化状態を把握しておく家庭血圧を重視する傾向があります。
高血圧治療ガイドラインによる
診療室血圧値の基準値
下記のように正常血圧の範囲は幅広く定義されています。
| 成人の正常血圧 | 120mmHg未満で80mmHg未満 |
|---|---|
| 成人の正常血圧の範囲 | 100/60mmHg以上120/80mmHg未満 |
| 正常高値血圧 |
収縮期が120~129mmHgの範囲内で拡張期が80mmHg未満 |
| 高値血圧 |
130~139/80~89mmHg |
| 高血圧の基準 |
140/90mmHg以上 |
高血圧の分類
高血圧は大きく3つに分類されます。
| Ⅰ度高血圧 | 収縮期が140~159mmHgの範囲で拡張期が90~99mmHgの範囲 |
|---|---|
| Ⅱ度高血圧 | 収縮期が160~179mmHgの範囲で拡張期が100~109mmHgの範囲 |
| Ⅲ度高血圧 | 収縮期が180mmHg以上、拡張期が110mmHg以上 |
薬以外で血圧を下げる方法
ハンドグリップ
ハンドグリップ運動は、最大の3割程度の力で握力を反復的に使用する運動で、アメリカ心臓学会(AHA)に認められた手軽にできるレジスタンス運動の一種です。本来はデジタル握力計などを使うことが推奨されていますが、ここではタオルを使って、ご家庭で簡単にできるタオルグリップ法を紹介します。
ハンドグリップのやり方
タオルでハンドグリップ運動を行う方法を以下に説明します。
- フェイスタオルを少し太めの筒状に丸める
- どんな姿勢でもかまわないので、自分の最大の3割程度の力を入れて右手で2分握る
- 手を拡げて1分間休む
- 同様に左手で2分間握る
- 同様に1分間休む
このサイクルを3~4回くりかえします。これを1日1回、週に最低3回程度行うだけで血圧が降下していきます。
インターバル速歩
インターバル速歩は、日本の熟年スポーツ医学の研究者が提唱した、誰もが自分の体力にあわせて、気軽に行うことができる有酸素運動です。有酸素運動は生活習慣病の改善・予防に効果があるとされています。
インターバル速歩のやり方
インターバル速歩は、自身の最大酸素摂取量の7割程度で歩く早歩きと、最大酸素摂取量の4割以下程度のゆっくり歩き繰り返し行います。手順を以下に示します。
- 胸を張って背筋をまっすぐに伸ばした正しい姿勢をとります
- 全力で歩く速さの7割程度の速度で速歩を3分間キープする
- 3分経ったら速度を緩めて、全力の4割程度のゆっくり歩きを3分間キープ
これを1セットとして、最低1日3セット以上を目標にしてください。
歩く際は、ふくらはぎのポンプ機能を意識しながら、つま先でしっかりと蹴り出し、かかとで着地するのが理想です。足を引きずるようにするところんでしまうこともありますので注意してください。
また、インターバル速歩が終わったら、30分以内を目安に牛乳やヨーグルトなどの乳製品を摂ることで、生活習慣病の改善効果が高まることがわかっています。
グーパー体操
グーパー体操は道具も薬も使わずに簡単に血圧を下げる方法で、テレビでも紹介されたことがあります。やり方は手をぎゅっと力を入れて少しの間握り血流を止め、ぱっと開くことで急激に血流を再開させます。それによって手の周辺の血管が刺激されて血行が改善します。末梢血管の血流が改善することで、大血管や心臓の負荷が低減し血圧が下がります。
やり方
- 手を心臓より下になるように下げる
- 片手の手のひらをぎゅっと強く握る(左右どちらからでもかまいませんが必ず片手ずつ)
- 握った手のひらをパッと開く
- この①~③を左右各1分ずつ、朝晩の1日2回行う
※注意:朝起きたてや運動後、食事後など血圧が高くなりやすい時間は避けて行ってください。
深呼吸
正しい深呼吸をすることで、血管を拡張させる効果と自律神経を整える効果が得られます。それによって、血圧も下がることが知られています。2~3回深呼吸を繰り返すと血圧は10mmHg程度下がるという報告があります。
正しい深呼吸は、まず息を肺が空になるほど口からゆっくり6秒ほどかけて吐き出し、その半分ぐらいの時間で鼻から息を吸うことです。
やり方
- 手をおへその下に置いて臍下丹田を軽く押すようにする
- 口から息をゆっくりと6秒程度かけて吐き出す。このとき口をすぼめるようにするとゆっくりはきだしやすくなる
- 鼻から3秒程度かけて息をゆっくり吸い込む
この②と③を2~3回くりかえすことで、血圧低下の効果を得ることができます。
ダイエット
肥満状態にあると一般の2~3倍高血圧になりやすいと言われています。特に皮下脂肪による肥満ではなく内臓脂肪型の肥満は、高血圧などの生活習慣病発症のリスクが高いことがわかっています。
これは、内臓脂肪の圧迫による血管への負担や、中性脂肪などの増加による血管内部への負担などが原因だと考えられています。
体重を1kg減らすことで、血圧は多い人で2mmHg程度下がるという報告もあります。無理のない範囲で体重を下げることに取り組みましょう。
食事
血圧を下げる食事として、近年DASH食という食事方法が提唱されています。これは1990年代に米国で開発され、日本でも高血圧学会により推奨されている食事法で、塩分、炭水化物、脂質を減らし、ミネラル、たんぱく質、食物繊維を積極的に摂ることで血圧を下げやすい体質にしようとするものです。
ミネラルの中でも、カリウム、カルシウム、マグネシウムの3種類は特に大切で、降圧効果が高いと言われています。また食物繊維は塩分や糖質の吸収を遅らせる効果があります。たんぱく質は身体の基礎をしっかりとさせるために必須の栄養分です。
また、血圧降下の基本として、身体に水分を保持する働きをする塩分摂取を減らすことが大切です。高血圧状態が続く方は、1日の塩分摂取を食塩相当で6g以内に抑えることが推奨されており、それによって20%もの血圧低下が得られたという例も上がっています。
代表的な塩分の多い食べ物と塩分量
| 食物(単位のないものは1杯) | 単位あたりの含有塩分 |
|---|---|
| 醤油ラーメン | 5.7g |
| きつねうどん | 5g |
| 寿司10貫 | 3.7g |
| カレーライス | 3.3g |
| ウインナー2本 | 0.8g |
睡眠
 睡眠状態と血圧は大きく関連していることが分かっています。睡眠時間が短すぎても、長すぎても高血圧になることが報告されていますので、適切な睡眠時間を確保するようにしましょう。
睡眠状態と血圧は大きく関連していることが分かっています。睡眠時間が短すぎても、長すぎても高血圧になることが報告されていますので、適切な睡眠時間を確保するようにしましょう。
- 睡眠時無呼吸症候群を指摘されている場合、適切な治療を行ってください。重症の場合はCPAPという装置が保険適用で利用可能です。その他の場合もマウスピースやナステントといった治療法があります。
- 眠りに入りにくい、眠りの質が低いといった方は、快眠を促すサプリメントも検討してみましょう
- 冷たい寝室や冷えたからだは眠りにくいため、寝室はしっかり加湿・暖房し、身体を暖めて休みましょう
- 寝る前に液晶画面を見ると脳が興奮してしまうため、パソコンやスマートフォンの使用を控えましょう
- 飲酒による入眠は睡眠の質を下げます。また喫煙習慣による不眠もありますのでどちらも控えましょう
血圧を下げる飲み物は?
 血圧を下げる飲み物は下記の通りです。
血圧を下げる飲み物は下記の通りです。
| 飲料 | 血圧を下げる効能・成分 |
|---|---|
|
ミネラルウォーター |
カリウム、カルシウム、マグネシウムを含む |
| 緑茶 | ポリフェノール(カテキン、タンニン) |
| ドクダミ茶 | デトックスと利尿効果が高い |
| ルイボスティー | ポリフェノールを多く含む |
| ノンアルコールの赤ワイン | ポリフェノールを多く含む |
| 飲用酢 | 酢酸から作られるアデノシンの血管拡張効果 |
| 牛乳、乳酸菌飲料 | カルシウム、カゼイン、乳清タンパクなど |
| 野菜ジュース | GABAなどの機能性成分 |
| ココア | ポリフェノールが豊富 |
一般的に、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどは血圧低下の効果が高いことが知られています。そのためそれらを含むミネラルウォーターや牛乳などの摂取が推奨されますが、ミネラルウォーターにはナトリウムが多い製品もありますので、成分表に注意しましょう。
一方、ワイン、ココア、ルイボスティーといった飲料にはポリフェノールが多く含まれており、活性酸素の働きを抑える効果や血管を拡張する効果が期待されます。なお、緑茶にはカフェインも多く含まれていますが、緑茶に同時に含まれるテアニンがカフェインの働きを抑えるため、睡眠を妨げることなく血圧にも良好であることがわかっています。
高血圧を助長する飲み物
飲むと血圧が上がるリスクのある飲み物もあります。以下に一例を挙げておきます。
- 砂糖入り炭酸飲料、スポーツドリンク、ジュース
- カフェインの多い飲料(栄養ドリンクなど)
- アルコール飲料
サイダーやコーラ等の炭酸飲料、スポーツドリンク、ジュース類などは、糖分が非常に多く含まれており、そのため血中のインスリン濃度が高くなることで、ナトリウムの排出能が低下し血圧を上げると言われています。
さらにカフェインは適量では血圧の低下効果もあるのですが、摂り過ぎることによって逆に血圧を上げるように働きます。コーヒーや緑茶といった自然な飲料はカフェインも多いのですが、その作用を打ち消すポリフェノールも多く含まれているので安全ですが、人工的にカフェインを多量に追加した栄養ドリンクなどは摂り過ぎに気をつけましょう。アルコール飲料も同様です。
血圧を下げる食べ物は?
 効果的に血圧を下げる食事を目指してみましょう。以下のような食物は血圧を下げる効果があるとされています。
効果的に血圧を下げる食事を目指してみましょう。以下のような食物は血圧を下げる効果があるとされています。
- バナナなどカリウムを多く含む果物類
- トマトなどGABAやリコピンを多く含む野菜類
- 雑穀米など食物繊維の多い雑穀類
- 食物繊維とカリウムの多い海藻類
- 食物繊維の多いきのこ類
- カリウムやマグネシウムの多い豆類・ナッツ類
- EPA、DHAの豊富な青魚(サンマ、ブリ、イワシ、アジなど)
血圧を下げるには、塩分の摂取を控えるのが効果的です。塩分の主成分であるナトリウムは身体に水分を貯留する働きがあり、そのため血圧が上昇してしまいます。専門家の研究によって日本人の場合、1日の塩分摂取量は食塩相当で6g以内が推奨されています。
食塩を減らすことに抵抗がある方は、調味料を増やすことでしっかりとした味を感じることも可能です。できればしょう油、味噌などの調味料も減塩タイプを選ぶと良いでしょう。
その他では、青魚のEPAやDHAは血液をさらさらにする効果が高く、それによって血圧も下がります。また、ナトリウム以外のミネラル類としてカリウム、マグネシウム、カルシウムなどは血管を強くしたりナトリウムを排出したりする役割があり血管のために重要です。さらに食物繊維は糖や塩分の吸収を遅らせる上、便通を安定させる効果もあり、血管への負担を減らします。その他、カカオやトマトなどに多いGABAというアミノ酸成分は、副交感神経を優位に保つことで、心因的なイライラなどを抑え血圧を安定させる働きもあります。
こうした様々な食品を、ご自身の嗜好などともあわせて積極的に摂取していくことで安定した血圧を保つことができます。