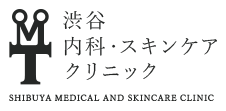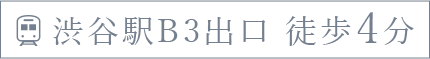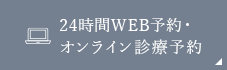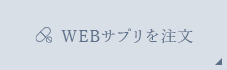- 慢性頭痛にお悩みの方へ
- 肩こり・首こりからくる頭痛「緊張型頭痛」
- ズキズキ・チカチカする「片頭痛」とは
- 片側の目の奥・こめかみに刺すような痛み「群発頭痛」
- 二次性頭痛
- 寝ても治らない頭痛
- 頭痛の診断
- 当院ならではの頭痛改善
- 当院で行う肩こり改善
- 診察の流れ
- よくあるご質問(Q&A)
内科専門医・日本頭痛学会員の
渡邉院長による頭痛専門外来
その頭痛、我慢しないで。
正しい治療でラクになれる。
慢性頭痛(片頭痛・群発頭痛など)は、**ズキズキ・ガンガンと急に起こる発作的な痛み**が特徴です。
痛みの最中に無理して
来院する必要はありません。
 痛みが落ち着いてからのご受診の方が、
痛みが落ち着いてからのご受診の方が、
- 丁寧な問診
- 適切な治療方針のご提案
ができ、ご本人のつらさも少なく済みます。
「耐えられない…」「薬が効かない…」という時も、事前にご相談いただければ対応いたします。
注意:こんな頭痛は救急対応が
必要です!
当院は入院設備がないクリニックのため、命に関わるような緊急の頭痛には対応できません。
次のような緊急性がある頭痛の可能性がある場合は、迷わず救急車を呼ぶ or 救急病院を受診してください。
- 何をしていたか覚えているくらいに突然に発症して一気に強くなる頭痛
- 人生最大の頭痛
- 麻痺もしくはしびれなどの神経症状を伴う頭痛
- 高熱に加え、頸の痛みを持つ患者さんの頭痛
- 痛すぎて意識消失をしてしまった頭痛
など
頭痛外来 診療実績
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2023年 | 752件 |
| 2024年 | 1604件 |
肩こり・首こりからくる頭痛
「緊張型頭痛」
最も一般的なタイプで、頭部を締めつけられるような鈍い痛みが特徴です。長時間のパソコン作業やストレス、姿勢の悪さが誘因となることが多く、首や肩の筋肉の緊張が関連していると考えられています。
緊張型頭痛の原因
- デスクワークなどで同じ姿勢を長時間続ける
- 猫背やうつむき姿勢などの姿勢の悪さ
- 長時間ブルーライトを凝視したことによる眼精疲労
- 睡眠不足による疲れ
- 運動不足による血行不良
- 精神的ストレスによる神経の緊張
- 気温や気圧の大きな変化
- 喫煙
など
緊張型頭痛の特徴
- 頭全体がズーンと重く、圧迫される感じがある
- 頭のてっぺんやこめかみなどに締め付けられるような痛みがある
- 重症例は少なく、吐き気は伴わない
- 夕方にかけて症状が悪化する
- 首や肩の筋肉が固くなる、肩こりを併発しやすい
など
緊張型頭痛の治療
頭痛発作が月に一度程度であれば、市販薬で対応することに問題ありませんが、市販薬にはカフェインが複合しており、依存性に注意が必要です。
生活に支障をきたす程度の痛みが週2日以上ある場合、もしくは受診を迷っている場合はお気軽に頭痛外来までご相談ください。
急性期ではアセトアミノフェンやNSAIDs系薬剤を中心にした治療を行います。
スマホを見ると頭が痛い
「スマホ頭痛」
最近急増している頭痛で緊張型頭痛の一種です。長時間の使用で筋肉が緊張し、後頭部を中心とした両側性の頭痛が起こります。ブルーライト対策や正しい姿勢、小休憩の導入が有効です。
ズキズキ・チカチカする
「片頭痛」とは
拍動性(ズキズキと脈打つような)痛みを伴い、しばしば吐き気や光・音に対する過敏症状を伴います。女性に多く見られ、ホルモンバランスの変化や睡眠不足、特定の食品などが誘因となることがあります。
片頭痛の原因
- 家族に片頭痛持ちの人がいる
- 低気圧が近づくなどといった気圧の変化
- チカチカする光や強い光
- 騒音や強い音
- 強い匂い
- ストレス
- ストレスからの解放
- 睡眠不足
- 寝すぎ
- 赤ワイン、カフェイン、チーズなど過剰摂取
- 空腹
- 月経周期や更年期などによる女性ホルモンの変化
片頭痛の特徴
- 脈打つような拍動性の痛みが、頭の片側または両側に起こる。
- 4~72時間程度持続する
- 激しい運動や、強い光や大きな音、特定の匂いで悪化する
- 吐き気、嘔吐などを伴う場合がある
- 頭痛が起こる前に目の前がチカチカする
- 頭痛発作中は、休息を必要とするが、痛みがおさまると日常生活に支障はない.
- 月に1~2回程度、またはそれ以上の頻度
片頭痛の治療
基本的に鎮痛薬または鎮痛薬と制吐薬を組み合わせて使用します。重症例ではトリプタンが推奨されています。また、重度の頭痛が72時間を超える場合や薬の効果が出ない場合には、鎮静麻酔薬や副腎皮質ステロイド薬を選択します。
サプリメント・食品
頭痛に聞く栄養素としては、オメガ3脂肪酸、ビタミンB2(リボフラビン)とマグネシウムなどが挙げられます。当院では、患者様の必要な栄養素を補うサプリメントなどをご提案させていただきます。
片側の目の奥・
こめかみに刺すような痛み
「群発頭痛」
比較的まれですが、非常に強い痛みが片側の目の奥に集中して起こり、涙や鼻水、眼瞼下垂などの自律神経症状を伴います。激しい激痛のため、別名で群発性頭痛と呼ばれることもあります。決まった時間帯に発作的に起こるのが特徴で、男性に多い傾向があります。
群発頭痛の原因
群発性頭痛の原因はいまだに解明されていない部分が多いですが、体温調節、食行動、睡眠などに重要な役割を担う脳内の視床下部という部位の機能異常、血管の拡張と炎症などが関与していると考えられています。
群発頭痛の特徴
群発頭痛では、片目の目の奥が痛くなるなどいくつか特徴的な症状があります。下記、群発頭痛で起こる主な症状となります。当てはまるものがありましたら、頭痛治療を専門とする当院までご相談ください。
- 片側の目の奥や眼球に激しい痛みが起こる(発作は毎回同じ片側)
- 1~2ヶ月程度のサイクルの中で、ほぼ毎日同じ時間帯に発症する
- 片側に起こる激しい痛みに伴い、汗、涙、鼻水が出る
- 痛みが頭や歯、下あごなどに広がることがある
- 明け方や深夜に痛みが起こりやすい
- 睡眠時間がずれると発作の時間もずれる
など
群発頭痛の治療
主に発作を抑える薬による薬物療法を行います。片頭痛の発作の治療に使用するトリプタン系の薬がしますが、痛みで飲み込めない場合は、皮下注射や点鼻薬を使用して速やかに症状を落ち着かせます。また、動くと症状が悪化する特徴があるため高濃度の酸素吸入を行います。
二次性頭痛
脳や血管の疾患、感染症など、明確な原因疾患に伴って生じる頭痛です。くも膜下出血や脳腫瘍、髄膜炎、側頭動脈炎などが代表的です。突然発症し、これまでに経験したことのない激しい痛みや、発熱、けいれん、意識障害などを伴う場合には、二次性頭痛の可能性があるため、早急な医療機関の受診が必要です。
頭痛は身近な症状である一方、危険な疾患のサインであることもあります。繰り返す頭痛に悩まされている方、痛みの質や頻度が変化した方は、早めに専門医の診察を受けることをおすすめします。正確な診断と適切な治療によって、頭痛の苦しみから解放され、快適な日常生活を取り戻すことができます。
寝ても治らない頭痛
 「十分に寝たはずなのに頭痛が治まらない」「眠っている間にも頭痛が続いている」といったお悩みには、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、高血圧、脳腫瘍などの疾患も、就寝中や起床時の頭痛を引き起こすことがあります。特に、睡眠中に呼吸が止まる・いびきが大きい・日中の強い眠気があるといった症状がある場合は、早めに当医院までご相談ください。
「十分に寝たはずなのに頭痛が治まらない」「眠っている間にも頭痛が続いている」といったお悩みには、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、高血圧、脳腫瘍などの疾患も、就寝中や起床時の頭痛を引き起こすことがあります。特に、睡眠中に呼吸が止まる・いびきが大きい・日中の強い眠気があるといった症状がある場合は、早めに当医院までご相談ください。
睡眠中・起床後に頭が痛い
~睡眠関連頭痛~
夜間の睡眠中や早朝の覚醒時に起こる頭痛を「睡眠関連頭痛」と呼びます。これは、不眠症や過眠、睡眠の質の低下、さらにはむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)といった睡眠障害が関与することがあります。睡眠の乱れは自律神経やホルモンのバランスを崩し、頭痛の誘因となることがあります。
対策
睡眠習慣を見直し、規則正しい生活リズムを整えることが第一歩です。寝る前のスマートフォン使用やカフェイン摂取を避け、心地よい睡眠環境を整えましょう。また、むずむず脚症候群のような基礎疾患がある場合は、医師による適切な治療が必要です。
頭痛の診断
頭痛は、一般的には他にこれという疾患が無い原発性頭痛です。しかし、副鼻腔炎や歯周病などのように片頭痛と似た症状を起こす疾患も有り、原因を正確に突き止めるためには、専門的な知識を持った医師による問診、検査などの診察を行って慎重に判断する必要があります。
頭痛ダイアリーをつけましょう
まずはどのような時に頭痛が起こるか、どの程度の期間続くのか、どの程度痛むのか、前駆症状の有無、頭痛時に吐き気や嘔吐、光や音への過敏性といった他の症状があるかなどについて詳しくお訊きします。また、食事や運動、飲酒習慣などの生活習慣についてお訊きすることもあります。そのため、ご来院される場合、これらの情報を記録した日誌のようなメモをご持参いただけると診断の参考となります。
当院ならではの頭痛改善
頭痛薬が効かない、
痛み止めの依存性が怖い、
副作用が気になる方へ
 当院では、頭痛のタイプ別に合わせて保険適応内で行うことができる治療を第一選択として行っています。ただ、中には頭痛薬が効かない、痛み止めの依存性が怖い、副作用が気になるといったお悩みを持つ方も少なくありません。そこで当院では幅広いニーズに応えられるよう、様々な治療法を取り扱っております。
当院では、頭痛のタイプ別に合わせて保険適応内で行うことができる治療を第一選択として行っています。ただ、中には頭痛薬が効かない、痛み止めの依存性が怖い、副作用が気になるといったお悩みを持つ方も少なくありません。そこで当院では幅広いニーズに応えられるよう、様々な治療法を取り扱っております。
無理に自費治療を進めることはありませんので、ご興味がある方はお気軽にご相談ください。
漢方
漢方薬は比較的副作用の少なく、妊娠中や授乳中の方でも安心して内服していただける漢方薬もございます。そのほか、気になる既往歴がある方など、頭痛のお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。丁寧な問診と診察でその方に合った治療を保険適応でご提案し、心身ともに健康でいるためのサポートをいたします。また、保険適応内のものを優先的にご紹介させていただきますのでご安心くださいませ。
高濃度ビタミンC点滴
高濃度ビタミンCを点滴で直接血管内に投与することで、コラーゲン生成が促進し、強力な抗酸化作用により美白効果、美肌効果だけでなく疲労回復効果、免疫力を高める効果までも期待できます。
プラセンタ注射
プラセンタは胎盤から抽出したエキスのことで細胞全体を活性化し、新陳代謝を促進することで皮膚や全身の細胞を元気にします。プラセンタは、美白、美肌、保湿、抗酸化作用、抗アレルギー作用、抗炎症作用、抗疲労効果、デトックス(肝機能改善)効果、ホルモンや自律神経のバランスを整える効果、自然治癒力を高める効果、血行改善効果など様々な作用と効果が期待できます。
にんにく注射
疲労は疲労成分が体内に溜まってしまっていることが原因です。ビタミンB1は疲労物質を代謝して除去することで肉体疲労はもちろんイライラや集中力の改善効果もあります。
痛み止め点滴
鎮痛薬を点滴で直接血管内に投与し、頭痛、生理痛などの痛みを速やかに改善します。
当院で行う肩こり改善
こりの原因は、長時間同じ姿勢を続けることにより首や肩回りの血流が滞ることで、発症します。他にも運動不足や、猫背や足を組む癖、冷風による冷え、ストレスなどによって起こります。最近では、長時間のパソコンやスマートフォンの使用によって若年層の方の訴えが増加しています。
こうした、原発的なこりの他に何らかの疾患が原因で2次的にこりが発生していることもありますので、ストレッチなどの運動やマッサージなどでもなかなかこりが治らない方は、お早めに当院にご相談ください。
プラセンタ療法(トリガー注射)による肩こり改善
慢性的な肩こりにお悩みの方へ、当院ではプラセンタを用いたトリガー注射療法を行っています。これは、肩こりの原因となる「トリガーポイント(発痛点)」に直接プラセンタを注射することで、こりや痛みを和らげる治療法です。
トリガーポイントとは、押すことでその部位だけでなく、周囲や離れた部位にも関連痛を引き起こす特徴のあるポイントです。いわゆる“ツボ”に似た位置にあることも多く、肩こりの根本的な原因とされる筋肉の緊張や血流不全に関与しています。
これまで肩こりに対しては、ステロイド薬を用いたトリガー注射が一般的でしたが、当院ではより自然で安全性の高い治療法として、プラセンタを使用した注射も選択いただけるようになりました。
プラセンタには、細胞の活性化や血行促進、抗炎症作用などが期待されており、筋肉のこわばりを和らげ、こりの改善を促します。
治療の目安としては、1〜2週間に1回程度の注射を継続することで、肩こりの軽減が持続しやすくなるといわれています。個々の症状に応じて、最適なタイミングや回数をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
肩の重だるさやこりが続き、日常生活に支障をきたしている方は、ぜひ一度、当院のプラセンタ注射療法をご検討ください。
ボツリヌス注射による肩こり改善
肩こりや肩太りは、主に肩や背中を支えている僧帽筋という筋肉が緊張して張ることが原因で引き起こされます。そのため、肩にボツリヌス注射を行うことによって僧帽筋を弛緩させ、肩こりや肩太りを改善して綺麗な肩ラインに整えることが可能です。
診察の流れ
1診察
 問診表をもとに医師が丁寧に診察します。
問診表をもとに医師が丁寧に診察します。
2検査
必要に応じて血液・尿検査をおこないます。内科的な病気が隠れていないか調べるために、複数の項目の検査をおこなう場合がございます。CTやMRI検査が必要な場合は、お近くの画像検査専門クリニックへご案内します。緊急性が高いと診断した場合はすぐに専門の医療機関へご紹介いたします。
3治療
経験豊富な医師が、患者様の症状やご要望に合わせ、内服薬の処方、漢方薬の処方、高濃度ビタミンC点滴、プラセンタ注射、にんにく注射、ボツリヌス注射などをご提案いたします。お気軽にご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
どのような頭痛は受診したほうが良いですか?
繰り返す頭痛や、天気・生理・ストレスで悪化する頭痛は、内科で相談可能な場合が多く、早めの受診がおすすめです。また、だんだん頭痛薬が効かなくなって使用量が増えてきた、頭痛薬を飲んだら湿疹が出たなどのケースではお早めにご来院ください。頭痛で生活に支障が出るといった場合は、脳の病気など重大な疾患が隠れてる場合があります。疑われる症状がある場合には、すぐに専門医療機関をご紹介いたしますので受診を迷われている方はお気軽にご相談ください。
ボツリヌス注射は頭痛に効果がありますか?
ボツリヌス注射は緊張しすぎた筋肉などを弛緩させる働きがあります。そのため、慢性頭痛である片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛それぞれに効果があるとされています。特に群発頭痛では頭部へのボツリヌス注射を行って2~7日程度経過すると頭痛が軽減し、7~8割の患者さんは1週間程度で頭痛が消失したという報告もあります。
鎮痛薬を飲み過ぎると良くないと言われますが、どのような副作用があるのでしょうか?
まず、鎮痛薬は一般的に服用しすぎることで、薬物乱用性頭痛を誘発することがあります。また、薬効に身体が慣れてしまうことで、薬が効きにくくなりさらに使用量が増えてしまうこともあります。
また非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に分類されるアスピリンやロキソプロフェン、イブプロフェンなどは、痛み物質であるプロスタグランジンの生成を抑制することで、鎮痛効果を得ていますが、プロスタグランジンは胃粘膜の保護効果や腎臓の血流促進効果もあるため、乱用することで胃粘膜が障害され、胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因となったり腎障害を起こしたりすることもあります。特に子どもや高齢者、腎障害のある方は使用に注意が必要です。
当院では、頭痛の治療と同時に、鎮痛薬の正しい使用方法などについても丁寧に説明しておりますので、いつでもご相談ください。