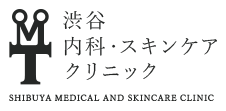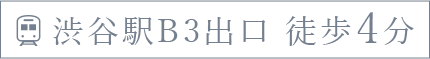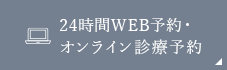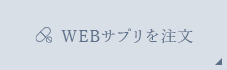高尿酸血症(痛風)とは
 尿酸は一定量体内に蓄えられ、それ以上になると腎臓から尿に含まれて排出されます。ところが、何らかの理由で尿酸が必要以上に体内に蓄積され過ぎてしまうと、血中に溢れてしまい、やがて結晶化します。この結晶が関節内に沈着し炎症を起こすと痛風発作となります。
尿酸は一定量体内に蓄えられ、それ以上になると腎臓から尿に含まれて排出されます。ところが、何らかの理由で尿酸が必要以上に体内に蓄積され過ぎてしまうと、血中に溢れてしまい、やがて結晶化します。この結晶が関節内に沈着し炎症を起こすと痛風発作となります。
好発部位は足の親指などです。痛風発作はしばらくすると治まりますが、高尿酸状態が治ったわけではなく、静かに進行して腎臓や心臓など様々な内臓に障害を起こすことが知られています。そのため、健康診断などで尿酸値の指摘があったら、必ず受診して尿酸値をコントロールする治療を受けるようにしてください。
高尿酸血症の症状
血液中の尿酸値が高くなることで関節に尿酸の結晶が沈着し、激しい痛みを伴う発作を起こす病気です。典型的には足の親指の付け根が赤く腫れて強い痛みが出ますが、くるぶし・膝・手などにも起こります。放置すると発作の頻度が増え、腎障害や尿路結石の原因となるため、早めの診断と治療が重要です。
高尿酸血症(痛風)の原因
 通常尿酸は体内に一定量以上増えると尿として排泄される仕組みになっています。尿酸が血中で過剰になる原因としては、尿酸が作られすぎているか、腎機能が低下し尿酸をうまく排出できないかのどちらかが考えられます。尿酸の産生が過剰になるのは、栄養過多による肥満などでプリン体が過剰に産生されてしまうことが主なケースです。腎臓・栄養過多のいずれのケースでも、生活習慣の乱れが大きく関係していることが多く、生活習慣病の1つに数えられています。
通常尿酸は体内に一定量以上増えると尿として排泄される仕組みになっています。尿酸が血中で過剰になる原因としては、尿酸が作られすぎているか、腎機能が低下し尿酸をうまく排出できないかのどちらかが考えられます。尿酸の産生が過剰になるのは、栄養過多による肥満などでプリン体が過剰に産生されてしまうことが主なケースです。腎臓・栄養過多のいずれのケースでも、生活習慣の乱れが大きく関係していることが多く、生活習慣病の1つに数えられています。
高尿酸血症(痛風)のリスク要因
- プリン体の多い食物(レバーや魚の肝類、魚卵など)の摂り過ぎ
- アルコール飲料の飲み過ぎ
- 甘い清涼飲料水の飲み過ぎ
- 水分摂取が少なめの方
- 激しい運動が多い方
- 男性で30歳を過ぎた方
- ストレスを溜めやすい方
- 内臓脂肪型肥満の方
- 血縁者に高尿酸血症を指摘されたり、痛風発作をおこしたりした方がいる
など
高尿酸血症の薬物療法
 基本として、食事や睡眠などの生活指導を行います。その上で、患者さんにあわせて尿酸値を下げる薬などによる薬物療法を行うことになります。ただし、急激に尿酸値に変動があると痛風発作が起こりやすくなるため、医師の指示をしっかりと守って治療に当たっていくことが大切です。
基本として、食事や睡眠などの生活指導を行います。その上で、患者さんにあわせて尿酸値を下げる薬などによる薬物療法を行うことになります。ただし、急激に尿酸値に変動があると痛風発作が起こりやすくなるため、医師の指示をしっかりと守って治療に当たっていくことが大切です。
痛風発作が起こったら
マッサージは禁忌?
俗に「風が吹いても痛い」と言われるほどの痛みをもたらす痛風発作が起こってしまったら、まずはクッションを積む、椅子の座面に足を置くなど痛む場所を高く保ち、安静にしながら冷やします。痛風発作は実は物理的な結晶のトゲトゲによる痛みではなく、炎症が起こっている部分を白血球が攻撃することで起こります。そのため、発作時に患部をマッサージしてしまうと、かえって血行が促されてさらに痛みが増してしまうことになりますので、安静が大切です。
発作が発症して24時間程度で痛みはピークを迎えます。その後はだんだんと痛みが薄れて行き、一般的には1週間程度で痛みは消えてしまいます。しかしそれで高尿酸血状態が治ったわけではありません。痛風発作が起こったら必ず受診するようにしてください。
痛風の原因となる
プリン体が多い食べ物
プリン体を食物から摂取しすぎることで、プリン体の燃えかすである尿酸が増えてしまうため、できる限り摂取量を抑える必要があります。
100gあたりのプリン体含有量
きわめて多い(300㎎以上)
肉類として鶏レバー、魚類として青魚類のタチウオ、魚類の肝としてイサキ、フグ、タラの白子、あん肝(酒蒸し)、魚類の干物としてマイワシ、カツオブシ、ニボシ、健康食品・サプリメントとしてDNA/RNA、ビール酵母、クロレラ、スピルリナ など
多い(200~300㎎)
肉類の内臓としてブタ、ウシのレバー、魚類の青魚類としてカツオ、マイワシ、甲殻類として大正エビ、オキアミ、魚類の干物としてマアジ、サンマ
中程度(100~200㎎)
肉類としてウシ、ブタ、トリのほとんどの部位、ほとんどの魚類、野菜類としてホウレンソウ(芽の部分)、ブロッコリースプラウト(若芽)など
少ない(50~100㎎)
肉類としてブタ(肩バラ、バラ、ロースなど)、ウシ(肩バラ、リブロース、ヒレなど)、ヒツジ(マトン、ラム)、加工肉類としてハム(ボンレス、プレス)、ベーコンなど、魚介類としてウナギ、ハモ、タラバガニなど、野菜類としてホウレンソウ(葉の部分)、カリフラワー、貝割れ大根、マイタケ など
極めて少ない(50㎎未満)
鶏卵、鶉卵、乳製品各種、上記以外の野菜類全般(穀類、豆類、きのこ類を含む)、加工食品として豆腐、ちくわ、かまぼこ、さつま揚げ など
プリン体はほとんどの食品に含まれており、完全に避けることは不可能です。プリン体は細胞の大切な要素の1つですが、人間は既に体内で十分なプリン体を持っているため、摂りすぎないように注意が必要です。
目安としての1日のプリン体摂取量の上限は400mg程度です。食品のプリン体含有量はインターネットなどでも入手できますので、それらを参考にしながらプリン体の摂取量をコントロールしていくと良いでしょう。