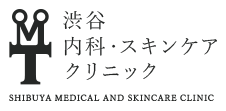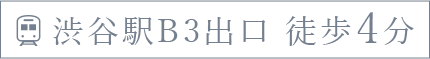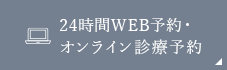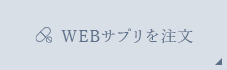トイレが近い、尿の回数が多い
~頻尿~
頻尿(ひんにょう)とは
 頻尿とは尿の回数や量が多くなっている状態です。ただし、尿の回数や量は人によって大きく異なり、一概に1日にどれだけの回数を超えてトイレに行くようになったら頻尿と言うことはできません。しかし、一般的に言えば1日に8回以上排尿があれば頻尿と言えるとされています。
頻尿とは尿の回数や量が多くなっている状態です。ただし、尿の回数や量は人によって大きく異なり、一概に1日にどれだけの回数を超えてトイレに行くようになったら頻尿と言うことはできません。しかし、一般的に言えば1日に8回以上排尿があれば頻尿と言えるとされています。
頻尿の原因
頻尿の原因は多岐にわたりますが、大別すると、膀胱の過活動や残尿と残尿量の増加、炎症や尿路感染、尿路の腫瘍などによる蓄尿量の低下、多尿症などによる尿量の増加と心因性のものに分類できます。
過活動膀胱
膀胱が突然収縮してしまい、尿が溜まっていない状態でも強い尿意を感じます。1回の尿量は少なく回数が増えてしまい、重症化するとトイレまで間に合わず少量の尿が漏れてしまう「切迫性尿失禁」を引き起こすこともあります。原因としては加齢による膀胱やその神経系の障害、前立腺肥大症による排尿障害、パーキンソン病や脳血管障害などによる膀胱のコントロール不全といった基礎疾患によるもの、基礎疾患が見当たらず原因不明の原発性のものなどがあります。日本ではこの過活動膀胱に悩む患者さんの数は推計で1250万人にも及ぶと言われています。
残尿量の増加
排尿しても全部を出し切れず、膀胱に尿が残ってしまうことを残尿と言います。加齢によってうまく膀胱が収縮できない、男性の場合前立腺肥大症や前立腺炎による尿の通過障害、女性の場合には子宮がんの手術で膀胱の神経が障害された場合などの他、糖尿病や腰の椎間板ヘルニア、直腸がんの手術による神経障害などで排尿障害が起こっていることが原因となっていることもあります。残尿量が増えることで、結果的に膀胱の蓄尿量を圧迫し頻尿が起こります。
多尿
何らかの原因で尿が作られ過ぎるのが多尿です。水分の摂り過ぎや利尿剤などの薬剤の効果が多尿の原因となることもありますが、糖尿病、尿崩症、高カルシウム血症、低カリウム血症などの病気や心因性の問題で尿量が増えることがあります。一回の排尿量は通常通りですが、尿が作られるペースが速いためトイレに行く回数が増えてしまいます。
尿路感染・炎症
膀胱や前立腺など、尿路周辺に炎症が起こると、膀胱の知覚神経が過敏となって尿意を感じることがあります。また、間質性膀胱炎という原因不明の病気は、常に膀胱に炎症が起こっている状態になり、頻尿になります。この病気は頻尿が長い間続いていて、膀胱が一杯になった状態で下腹部痛が起こるという症状が現れます。
腫瘍
膀胱のがんは一般的には血尿が現れることで気づくことが多いのですが、がんのできた部分によっては神経が刺激されることで頻尿の症状を現すことがあります。
心因性
膀胱から尿道にかけての病気や、その他の頻尿を起こす病気が見当たらず、尿量が増えているわけでもないのに、すぐに尿意をもよおしトイレに通ってしまう場合、心因性の頻尿が考えられます。夜寝ている間は頻尿の現象がおこらないのが特徴で、朝起きた時に尿が溜まりすぎているということもありませんが、起きている間はいつもトイレのことが気になって日常生活に支障を来すこともあります。
頻尿に対する対処の方法
頻尿が起こると、頻尿によるストレスも重なってQOL(生活の質)は大きく低下します。尿に関することのため、つい人に相談するのをためらってしまうことがあるかもしれませんが、そういった我慢は禁物です。頻尿の原因は様々ですが、何らかの重大な病気が関連していることも有り得ますので、お早めに泌尿器科を受診することをお勧めします。
その際、頻尿の状態を記録した排尿日誌を付けて、資料として持参すると診断のための参考になります。排尿日誌のテンプレートもありますが、記録するのは、トイレに行った時間、排尿の有無と排尿があったときの排尿量、水分摂取の時間と量を1日に1シート、都合3日分程度を記録してください。
この日誌を見て、水分摂取の問題の場合は生活指導となりますが、その他にも原因疾患がないか、様々な検査を行い、病気が見つかった場合にはその治療を行います。
夜間、何度もトイレで起きる
~夜間尿~
夜間頻尿とは
 夜、眠っている間に1回以上トイレに起きてしまう場合、夜間頻尿といいます。睡眠の質も低下し、日常生活に差し障りが出やすくなることや、高齢者の場合、暗い中での移動で転倒の危険が増えるなどで注意が必要な状態です。
夜、眠っている間に1回以上トイレに起きてしまう場合、夜間頻尿といいます。睡眠の質も低下し、日常生活に差し障りが出やすくなることや、高齢者の場合、暗い中での移動で転倒の危険が増えるなどで注意が必要な状態です。
夜間頻尿の原因
夜間頻尿の原因も昼間の頻尿と同様1)尿量の増加と2)膀胱容量の減少が原因となり、さらに3)睡眠障害も加わります。これらの症状の原因となる他の病気がある場合と、他の病気が見つからない場合があり、しっかりと原因を究明して治療にあたることが大切です。
1)多尿・夜間多尿
何らかの原因によって日中も夜間も変わらず尿量が多いのが多尿ですが、夜間多尿は通常睡眠中はホルモンの働きによって抑えられる尿量がホルモンの分泌が何らかの原因で減少し、夜間のみ多尿になります。どちらのケースでも原因疾患が無いかどうか確認する必要があります。
①多尿による夜間頻尿
昼夜を問わず尿量が増えるために、夜間就寝中も尿意で目覚めてしまいます。原因はコントロールがうまくできていない糖尿病などの内科系の病気や、利尿剤系の薬の作用、水分の摂り過ぎなどが主なものです。多尿の基準値は体重1kgあたり1日の尿量が40mLを超えたあたりにあります。つまり体重70kgの人だと40mL×70kg=2800mLとなり、1日の尿量が2800mL以上になると頻尿と言うことができます。
②夜間多尿
通常、就寝中はADHという抗利尿ホルモンが分泌され、尿量は減少します。しかし何らかの原因によって就寝中にADHの分泌が減少してしまい、就寝中の多尿が見られるようになることがあります。原因は加齢によるホルモンバランスの変化、何らかの原因による内分泌異常、高血圧や心臓の病気、腎機能障害などが考えられます。またそれ以外に、睡眠時無呼吸症候群や激しいいびきなどで睡眠の質が低下し、交換神経優位になっているために夜間頻尿となる例もあります。
2)膀胱容量の減少
膀胱容量の減少が起こるのは膀胱の神経が過敏になってしまった状態や、多飲、神経性のもの、男性の場合前立腺肥大症などの病気が考えられます。膀胱容量が低下していますので、日中の頻尿も見られるケースが多くなっています。
①過活動膀胱
膀胱の神経が過敏になっていて、尿が少しでも溜まると尿意をもよおすケースや、膀胱が意に反して収縮してしまうために切迫した尿意をおぼえてしまうケースで、どうしてもトイレに行きたくなる尿意切迫感、我慢できずに少し尿漏れを起こしてしまう切迫性尿失禁などの症状が現れます。加齢による神経系の障害などが主な原因ですが、中にはパーキンソン病や脳血管障害などで神経が障害されて起こるケースもあります。
②前立腺肥大症
男性の生殖器系の1つである前立腺は加齢によって肥大してきます。前立腺は膀胱の下で尿道を取り囲むように存在していますので、肥大によって排尿障害が起こり、そのために残尿が増えたり、膀胱の神経が過敏になったりすることで頻尿が起こります。
③その他
原因不明で膀胱に炎症が慢性的に起こる間質性膀胱炎では炎症が続くことで膀胱の神経が過敏になることがあります。また女性特有の骨盤臓器脱では、多臓器が膣内に脱することで膀胱が圧迫されたり、膀胱自体が脱することで刺激されたりして夜間頻尿になることがあります。
3)睡眠障害
様々な理由で眠りが浅くなっていると、すぐに目覚めることで交換神経優位となり、尿が日中と同様に作られてしまうケースや、睡眠中に溜まった尿のために目覚めるとトイレ②行きたくなるなどが考えられます。
トイレが近いと思ったら
排尿日誌をつけましょう
夜間頻尿を起こす原因は様々ですが、その裏に何らかの病気があるのか、それとも加齢による自然な劣化なのかなど、はっきりと原因をつきとめることで、適切な治療を行うことができます。そのためにも、夜間頻尿の症状があれば、歳だから仕方ないなどと思わずに、泌尿器科に相談することが大切です。
診療時にご自身である程度排尿日誌をつけておいていただけると、おおいに診断の助けとなり、医師の立場としてはありがたいです。
排尿日誌は、日中、夜間を問わず、排尿のあった時間、量、水分摂取の時間、量などを記録するもので、テンプレートはインターネットでも入手することができます。
尿量は、少し大きめの計量カップのようなもので計ると良いでしょう。
その結果、夜間の尿量が毎回の排尿ごとに200~300mL程度ある場合には、多尿か夜間多尿が原因、毎回の排尿量がおよそ100mL以下と少なめの場合は膀胱容量が減少していると大きく切り分けができます。
原因別の治療
1)多尿・夜間多尿
何らかの原因疾患があって多尿・夜間多尿となっている場合は、それぞれの原因疾患の治療を行います。考えられる病気としては、コントロールの悪い糖尿病、高血圧症、虚血性心疾患、慢性、急性の腎機能障害、睡眠時無呼吸症候群などです。また服薬中の薬剤が原因となっている場合は、休薬や薬剤の変更などを検討します。
就寝前の過剰な水分摂取はかえって夜間頻尿による睡眠の質の低下につながることがあります。就寝前の水分摂取は控えめにしましょう。
近年では尿崩症などによる多尿の治療にデスモプレシンという点鼻薬なども利用できるようになっており、薬物療法の選択肢も拡がってきています。
2)膀胱容量の減少
 過活動膀胱の場合は、以下の薬を検討します。
過活動膀胱の場合は、以下の薬を検討します。
抗コリン薬
膀胱の筋肉を収縮させる働きのある神経伝達物質であるアセチルコリンの働きを阻害します。
β3受容体作動薬
膀胱の筋肉の緊張を緩める作用のあるノルアドレナリンを働きやすくします。
α1アドレナリン受容・
PDE5阻害薬・5α還元酵素阻害薬
前立腺肥大が原因の場合に使用します。状況によっては前立腺切除に至ることもあります。
間質性膀胱炎や骨盤臓器脱の場合は、根治治療のため手術療法となるケースが多くなっています。
3)睡眠障害
睡眠障害が原因となって夜間頻尿が起こっている場合、睡眠時無呼吸症候群などの原因疾患がある場合にはその疾患に対する治療が大切です。それ以外の場合は、生活習慣の見直しなどからはじめて、それだけでは十分な効果が得られない場合、睡眠導入剤や睡眠薬などの処方も検討します。