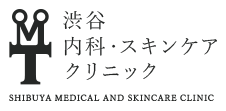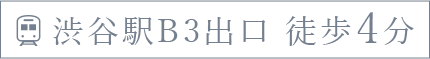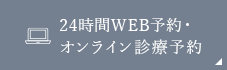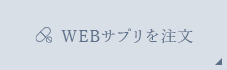息切れとは
 息切れとは、酸素不足などが原因で激しい呼吸を繰り返す呼吸器症状です。息切れを起こす原因は多岐に渡り、中には重篤な病気が原因の場合もあります。発症の目安としては、普段は問題なかった階段や坂道で息切れを起こす、深呼吸しないと息苦しくなる、すぐに呼吸が荒くなる、浅く早い呼吸を繰り返すなどが挙げられ、このような症状が現れている場合にはできるだけ早めに当院までご相談ください。
息切れとは、酸素不足などが原因で激しい呼吸を繰り返す呼吸器症状です。息切れを起こす原因は多岐に渡り、中には重篤な病気が原因の場合もあります。発症の目安としては、普段は問題なかった階段や坂道で息切れを起こす、深呼吸しないと息苦しくなる、すぐに呼吸が荒くなる、浅く早い呼吸を繰り返すなどが挙げられ、このような症状が現れている場合にはできるだけ早めに当院までご相談ください。
動悸が伴う息切れ、
考えられる病気は?
 息切れを起こす主な原因は酸素不足です。私たちは呼吸によって取り入れた酸素を肺で吸収し、血液を通じて全身に送り届けます。しかし、何らかの原因によって身体が酸素不足に陥ると、肺がより多くの酸素を取り入れようとして呼吸が荒くなり、息切れを引き起こします。
息切れを起こす主な原因は酸素不足です。私たちは呼吸によって取り入れた酸素を肺で吸収し、血液を通じて全身に送り届けます。しかし、何らかの原因によって身体が酸素不足に陥ると、肺がより多くの酸素を取り入れようとして呼吸が荒くなり、息切れを引き起こします。
息切れを起こす原因疾患の中には命の危険を伴うような重篤なものも含まれているため、今までは問題なかったようなちょっとした動作で息切れを頻発する場合には、自己判断で放置せずに速やかに当院までご相談ください。
息切れを起こす主な原因は以下となります。
心臓関連の問題
心臓に何らかの異常が生じると、血液を全身に運搬する機能が低下して身体が酸素不足に陥り、息切れを起こすことがあります。考えられる病気としては、心房細動や心不全、弁膜症などが挙げられます。
肺関連の問題
肺に何らかの異常が生じると、酸素を取り入れる機能が低下して動悸や息切れを起こすようになります。考えられる病気としては、肺炎や気管支喘息、肺塞栓症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが挙げられます。
不安やストレス
極度の不安感や過度なストレスは、自律神経のバランスを乱して動悸や息切れを引き起こします。また、これらの症状はパニック障害や不安障害によって現れることもあります。
貧血
貧血とは、酸素を全身に運搬する役割を担っている赤血球や赤血球を構成するヘモグロビンに何らかの異常が起きることで身体が酸素不足に陥る状態を言います。酸素が不足することで動悸や息切れなどの症状を引き起こします。
運動や身体的な活動
激しい運動をすると、失った酸素を補うために呼吸が荒くなり、一時的に動悸や息切れに似た症状を起こします。これらは正常な反応ですが、軽度な運動でも動悸や息切れを起こしたり、運動後に動悸や息切れが長時間継続する場合には心臓や肺に何らかの異常が生じている可能性があるため、できるだけ早めに医療機関を受診するようにしましょう。
息切れを伴う疾患
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、肺に慢性的な炎症が起きることで肺機能が低下し、息切れや呼吸不全などの症状を引き起こす病気です。主な原因は長期間に渡る喫煙で、タバコの有害物質によって肺組織が徐々に破壊されることで引き起こされます。その他では、化学物質が原因となることもあります。なお、一度破壊された肺組織は二度と再生しないため、改善には早期発見・早期治療が不可欠となります。
また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さんは感染症のリスクも高まるため、インフルエンザなどでも重症化する恐れもあり、注意が必要です。
気管支喘息
 気管支喘息とは、アレルゲンを吸い込むことで気管支に慢性的な炎症が生じ、呼吸困難などの症状を引き起こすアレルギー性疾患です。気管支喘息の発作には、呼吸の際にヒューヒュー・ゼイゼイという喘鳴を伴う特徴があります。
気管支喘息とは、アレルゲンを吸い込むことで気管支に慢性的な炎症が生じ、呼吸困難などの症状を引き起こすアレルギー性疾患です。気管支喘息の発作には、呼吸の際にヒューヒュー・ゼイゼイという喘鳴を伴う特徴があります。
治療では、気管支の炎症を抑えることや炎症によって狭窄した気管支を広げる処置を行います。また、日常生活の中でアレルゲンを遠ざける取り組みも大切になります。
貧血
貧血とは、酸素を体全体に運搬する役割を担っている血液中の赤血球や赤血球を構成しているヘモグロビンの量が減少した状態です。
主な原因は鉄分の摂取不足となります。また、胃潰瘍など消化管が出血する病気でも貧血を引き起こします。これらを鉄欠乏性貧血と言います。
一方で、腎不全などで腎臓機能が低下し、血液が十分に生成できなくなることが原因で引き起こされる貧血は、腎性貧血と言います。
貧血を起こすと、身体が酸素不足に陥って息切れやめまい、頻脈などの症状が現れます。
心不全
 心不全とは、何らかの原因によって心臓のポンプ機能が低下し、体全体に十分な血液を送り出せなくなった状態の病気です。主な原因は心疾患ですが、高血圧や過度な飲酒、肥満、過度なストレスの蓄積などの生活習慣の乱れの他、加齢や貧血、ウイルス感染症、睡眠時無呼吸症候群、腎臓病、甲状腺機能亢進症、化学療法、放射線療法などが原因となることもあります。特に睡眠時無呼吸症候群と心不全を併発している場合には命の危険を伴うこともあるため、注意が必要です。
心不全とは、何らかの原因によって心臓のポンプ機能が低下し、体全体に十分な血液を送り出せなくなった状態の病気です。主な原因は心疾患ですが、高血圧や過度な飲酒、肥満、過度なストレスの蓄積などの生活習慣の乱れの他、加齢や貧血、ウイルス感染症、睡眠時無呼吸症候群、腎臓病、甲状腺機能亢進症、化学療法、放射線療法などが原因となることもあります。特に睡眠時無呼吸症候群と心不全を併発している場合には命の危険を伴うこともあるため、注意が必要です。
狭心症
狭心症とは、心臓に酸素や栄養を送り届ける役割を担う冠動脈が狭窄を起こし、心筋が酸素不足に陥った状態の病気です。主な原因は動脈硬化で、放置すると冠動脈が完全に閉塞して心筋梗塞へと進行する恐れもあります。
主な症状は、息切れや呼吸困難、胸を締め付けられるような胸痛などになります。また、狭心症の状態で激しい運動をすると狭心症発作を起こす可能性もあり、注意が必要です。
不整脈
不整脈とは、心臓の拍動に異常が起きている状態の病気です。不整脈には、脈が速くなる頻脈、脈が遅くなる徐脈、脈が飛ぶ期外収縮の3つのパターンがあり、動悸や息切れが伴う場合があります。
主な原因は拡張型心筋症や肥大型心筋症、弁膜症、心筋梗塞などの心疾患ですが、その他でも高血圧や肺疾患、甲状腺疾患、睡眠時無呼吸症候群などが原因で引き起こされることもあります。
症状が軽度の場合には経過観察に留めますが、中には早期に治療が必要なケースもあるため、気になる症状が現れている場合にはできるだけ早く当院までご相談ください。
腎機能障害
腎機能障害を起こすと十分に尿が生成されなくなって体内に余分な水分が蓄積するようになります。これにより、心臓の負担が増大して息切れなどの症状を引き起こします。また、むくみや胸水、腹水などを引き起こすこともあります。
更年期障害
更年期障害とは、閉経の前後5年間に女性ホルモンの分泌量が低下し、自律神経のバランスが乱れて様々な症状を引き起こす病気の総称です。主な症状は、めまいや肩こり、イライラ、全身倦怠感、動悸、息切れなどの他、急激なほてりや発汗などを伴うホットフラッシュなどが挙げられます。また、女性ホルモンが不足することで脂質異常症や骨粗鬆症を併発することもあり、注意が必要です。
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
バセドウ病とは、何らかの原因によって甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、頻脈など様々な症状を引き起こす病気です。主な症状は頻脈の他に微熱や息切れ、疲労感、手足の痺れ、手の震え、体重減少、発汗、喉の腫れなどが挙げられます。
一般的に女性に多い傾向があり、症状が更年期障害に類似していることから更年期障害と勘違いして放置されてしまうケースも多く見られます。なお、バセドウ病は現在では医療機関で適切な治療を受けることで改善が期待できます。
脳出血
脳出血とは、高血圧などが原因で脳内の動脈が破裂して出血を起こしている状態の病気です。特に激しい寒暖差などによって血圧が急上昇した際に発症する傾向があるため、冬場の風呂場などでは注意が必要です。
主な症状は激しい頭痛や吐き気、動悸、息切れ、めまい、意識障害、言語障害などで、治療が遅れると重篤な後遺症を起こす恐れがあるため、症状が現れたらためらわずに救急車を呼んで治療を行ってください。
心筋梗塞
心筋梗塞とは、心臓に酸素や栄養を届ける役割のある冠動脈が閉塞を起こした状態の病気です。主な症状は、締め付けられるような激しい胸痛やみぞおち痛、吐き気、動悸、息切れ、めまい、失神などの他、歯や喉、顎、腕など心臓から離れた場所にも痛みが生じることもあります。
心筋梗塞は放置すると心筋が壊死して命の危険を伴うため、症状が現れたらためらわずに救急車を呼んで治療を行ってください。
息切れの検査
 息切れを引き起こす原因は多岐に渡り、中には呼吸器疾患や心疾患の可能性もあるため、検査では血液検査に加えて心電図検査、胸部レントゲン検査、呼吸機能検査、呼気NO検査、パルスオキシメーターによる血中酸素濃度測定検査などを実施して原因の特定を図ります。また、これらの検査結果によってはCT検査や血管造影検査、換気血流シンチグラフィーなどを追加で行うこともあります。なお、これらの追加検査が必要と判断した場合には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
息切れを引き起こす原因は多岐に渡り、中には呼吸器疾患や心疾患の可能性もあるため、検査では血液検査に加えて心電図検査、胸部レントゲン検査、呼吸機能検査、呼気NO検査、パルスオキシメーターによる血中酸素濃度測定検査などを実施して原因の特定を図ります。また、これらの検査結果によってはCT検査や血管造影検査、換気血流シンチグラフィーなどを追加で行うこともあります。なお、これらの追加検査が必要と判断した場合には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
息切れの治療
 息切れを起こしている原因疾患が心不全や不整脈、弁膜症、冠動脈疾患の場合には、原因疾患の治療を行って症状の改善を図ります。具体的には、食事習慣の見直しや適度な運動習慣の取り入れなどの生活習慣の改善の他、薬物療法を実施します。心不全が原因の場合には、これらの治療に加えて水分や塩分の摂取制限を合わせて行います。
息切れを起こしている原因疾患が心不全や不整脈、弁膜症、冠動脈疾患の場合には、原因疾患の治療を行って症状の改善を図ります。具体的には、食事習慣の見直しや適度な運動習慣の取り入れなどの生活習慣の改善の他、薬物療法を実施します。心不全が原因の場合には、これらの治療に加えて水分や塩分の摂取制限を合わせて行います。
当院では、総合内科専門医の資格を持つ医師が、豊富な診療経験を基に、患者様に最適な治療法を提案いたします。息切れは、命に関わる危険な疾患が潜んでいる可能性もございますので、気になる症状がございましたら、早めに当院までご相談ください。